02 「誰とでも接することができる人」という評価
03 学生時代に経験した変化と挫折
04 働きながら得た「生きていくためのスキル」
==================(後編)========================
05 LGBTだって悩みの中身はみんなと一緒
06 簡単かつ正確に “安心” に導く役目
07 無理して「普通」にならなくてもいい
08 悩みを抱え込まず、踏み出してほしい一歩
01 “中の上” で生きてきた僕の生業

「将来設計士」という仕事
現在の仕事の主軸は、保険営業。
時には、ファイナンシャルプランナーとして、将来に関する相談を受けることもある。
「保険業界に入って13年経ちますが、数回の転職、独立を経験してきました」
「今はホロスプランニングって会社に所属してるんですけど、歩合給なので、すべて自己責任ですね」
保険営業は、野球選手に近いイメージかもしれない。
所属するチームが変わっても、打席に立ってボールを打つことに変わりはない。
保険営業も、人に会い、保険を提案することに変わりはないのだ。
「僕のお客さんは、99%が個人の方で、法人はほとんどないんです。個人の方が、自分に合ってますね」
「保険の仕事の目的は、お金に困らない人生のお手伝いをすることです」
ホロスプランニングでは、「将来設計士」という肩書で活動している。
「お客さんがどう生きたいのか、それに対して僕ができることは何か。そこを考える仕事だと思ってます」
「会社としても、 “総合生活支援産業” を目指してますね」
接点を持ちやすいポジション
「僕はずっと “中の上(ちゅうのじょう)” の人生なんです」
学生時代、学級委員を務めた経験はあるが、成績は中の上。
高校も大学も、偏差値55。
特別スポーツが得意なわけでもなく、派手に目立つタイプでもなかった。
「でも、中の上で良かったな、って思います(笑)」
「僕みたいなポジションって、優秀な子たちともやんちゃな子たちとも、接点を持てるんです」
「その関係値が、今の仕事にも生きてくるんですよね」
保険営業は、保険を売る仕事ではなく、人と会い、コミュニケーションを取る仕事。
自分は、優秀な人にも破天荒に生きている人にも共感でき、どちらにも話を聞いてもらいやすい。
「中の上って、うまい立ち位置なんですよね(笑)」
「GID保険相談窓口」設立
仕事のかたわら、「GID保険相談窓口」を運営している。
「ホロスプランニングに入る前から、続けている事業です」
「たまたまトランスジェンダーの方を紹介されたことがきっかけで、スタートしました」
「保険に入れなくて困っているGID(性同一性障害)の人が多いから、相談に乗ってもらえないか?」という理由で、紹介された。
話を聞いていると、若い方の保険に関する知識が少ない、という改善点が見えてくる。
「LGBT当事者の方が難しいと思っていることが、僕にはまったくハードルに感じなかったんです」
「その時は、まだSRS(性別適合手術)や治療に関する知識はなかったけど、保険に関する知識はあったので、力になれるんじゃないかって」
「『その保険がダメでも、こっちの保険ならOKですよ』って、すんなり提案できました」
相談者が協力してくれたこともあり、「GID保険相談窓口」の開設に至った。
「でも、それまではLGBT当事者の知り合いがいなかったし、存在を気にも留めていなかったんですよね」
02「誰とでも接することができる人」という評価
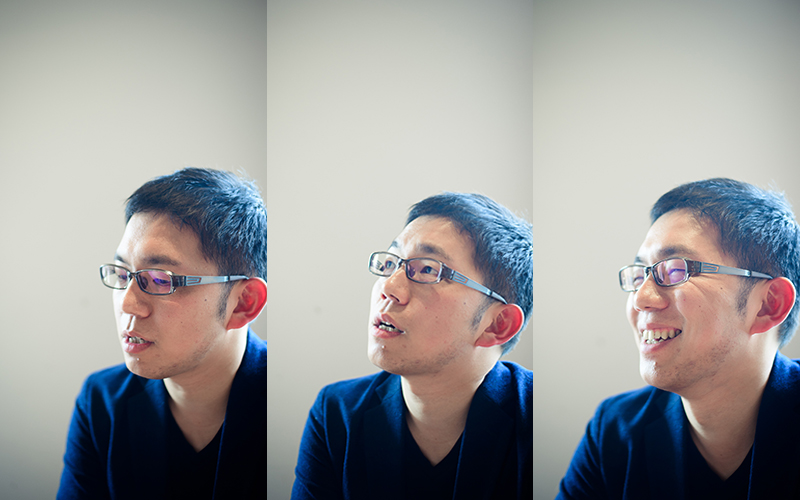
フットワークの軽い少年
家族は、両親と2人の妹。
「2歳下、4歳下の妹がいるからか、周りからよく『面倒見がいい』って、言われますね」
「今は仕事で全国を飛び回ってるけど、昔からフットワークは軽かったみたいです(笑)」
幼稚園児の頃、小学3年生のいとこと2人で新幹線に乗り、青森のいとこの家に行った記憶がある。
同じ時期に、2歳下の妹とバスに乗り、祖父の家にも遊びに行っていた。
「子ども2人で新幹線やバスなんて、今だったら心配しますよね(苦笑)」
小学校高学年から中学生にかけては、京都から神奈川の祖母の家まで、1人で鈍行列車を乗り継いで行っていた。
「小さい頃から、遠出することには何の抵抗もなかったんですよ」
「両親からも、しっかりした子だ、って認識されてたんだと思いますね」
辞められなかった習い事
小学校から現在まで、バレーボールを続けている母は、スポ根タイプ。
「『時間を守れ』『期日を守れ』って、よく言われてましたね」
「習い事は、『あんたがやりたいって言ったんでしょ』って、辞めさせてくれなかったです(苦笑)」
物心がつく前から、書道教室に通っていた。
小学4年生で神奈川から京都に引っ越した後も続けたが、京都の書道教室の先生がとにかく厳しい。
「書道やりたくない」と打ち明けると、母から「あんたがやりたいって言ったんでしょ」と返されてしまう。
「自分で『やる』って言った記憶は、ほとんどなかったんだけどな(笑)」
一方、文化系の父の教育方針は、「子どものやりたいようにやらせる」。
「両親は真逆で、はっきりしてましたよ」
「それぞれの教育方針が良かったのか悪かったのか、今もわかんないですけどね」
学級員に立候補するタイプ
中高生の頃の自分は、学級委員に立候補していた。
「目立ちたいわけではなくて、『誰もやらないんだったら俺がやる』みたいなタイプ」
「誰も立候補しないで、もぞもぞした時間をかける意味って、ないじゃないですか。だからといって、まとめ役が得意というわけでもないんです」
大人になってからも、同窓会の幹事を任されるが、よく言われることがある。
「三浦君は、その場にいてくれるだけでいい」
リーダーシップを発揮するわけではないが、全体の橋渡し的な役割は嫌いではない。
「周りを見ながら、何かあれば調整する役回りは、自分としてもしっくりきますね」
中学生時代の通信簿で、担任から「あなたは男女問わず、誰とでも接することができる人です」と、評価された。
「先生からの言葉はいまだに覚えていて、時間が経つほど身に染みますね」
「いろんな人と会う今の仕事に、通じてるところがあるんじゃないかなって」
03学生時代に経験した変化と挫折
地元のコミュニティ
小学4年で京都に引っ越した時、ぶつかったのは関西弁の壁。
「環境が変化して、言葉の違いにも戸惑いましたね」
「でも、困ったのは最初の1カ月くらい。子どもって、馴染むの早いですから」
転校生だから、といじられるようなことはなかった。
「多分、4月末に地元のサッカークラブに入ったのが、良かったんだと思います」
クラスメイトから誘われたサッカークラブの練習場は、家から徒歩30秒のグラウンド。
入らない理由がなかった。
「サッカークラブには隣のクラスの子もいたから、一気に輪が広がったんです」
「地元のコミュニティに入るって大事だし、京都は特に重んじられますからね」
人生初の挫折
地元の中学を卒業し、スポーツ、特に球技の成績がいい私立の男子高校に進む。
「中学でサッカー部のキャプテンを務めたこともあって、サッカーを続けたかったんです」
「・・・・・・でも、サッカー部は3日で辞めました(苦笑)」
強豪校のサッカー部は、1年生だけで部員が50人以上。
同期は、プロクラブのジュニアユースや都道府県選抜に選ばれた猛者ばかり。
「『真面目だから』って理由だけでキャプテンをしていた僕なんか、話にならないですよ(苦笑)」
“中の上” で生きてきた自分にとって、人生で初めての挫折。
両親には、「サッカーがしたくて入学したのに、申し訳ありません」と、頭を下げた。
「母からは『何のために私立の学費払ったと思ってるの!』って、怒られましたね」
「父は、『最初から無理だと思ってた』って(苦笑)」
一生続けられる趣味
サッカー部を辞めた後、向かった先は吹奏楽部。
「音楽の授業の一環で、クラシックギターを始めたこともあって、音楽いいなと」
「中学生の時に体育と音楽だけ成績5を取ってたし、友だちが吹奏楽部だったから、じゃあ俺も入る、みたいな」
担当した楽器はフルート。
自分が入部した時点で、トランペットやサックス、パーカッションといった男子の花形は埋まっていた。
「どちらかと女子の花形といわれるフルートやホルンしか残っていなくて、フルートを選びました」
挫折の末に始めた吹奏楽は、今でも続けている。
「大学からオーケストラに所属して、今も年に数回、演奏会に出てます。楽器は、一生ものの趣味だと思いますね」
サッカーを一生続けることは難しいが、楽器は何歳になっても続けられる。
「世代関係ない趣味だから、これからも続けていきたいです」
04働きながら得た「生きていくためのスキル」

女性社会で生きるスキル
大学卒業後、大手中食メーカーに就職。デパ地下の店舗に配属された。
「新卒で店舗に配属されて、いきなり50人のアルバイトがいるんですよ」
右も左も分からない状況で、唐突にマネジメント業務が発生する。
朝から夕方までは主婦、夕方以降は女子大生が多い職場は、まさに女性社会。
「最初は、やりづらくてしょうがなかったです(苦笑)。でも、そのマネジメントの経験で、女性の変化に気づくのは早くなりました」
職場に入る時の「おはよう」の声のトーンで、体調を判別できるようになっていく。
「褒めると伸びる子、厳しくすると覚える子とか、それぞれの特性も、わかるようになりましたね」
約2年半で転職することになるが、デパ地下での経験には意味があった。
「保険相談の8~9割は、女性なんですよ。だから、デパ地下で養ったスキルは生きてます」
保険営業の難しさ
保険の仕事を始めたのは、今から12年ほど前。
「もともと金融業には興味があって、個人のお客さんのFP相談とかやりたいな、って思ってたんです」
「保険会社に絞っていたわけではないんですけど、僕がやりたいことの理想に近かった会社がソニー生命保険でした」
「歩合給だって知らないで入社したので、やべぇな、って思いましたよ(笑)。しかも、ソニー生命保険にいる間は、全然売り上げを出せなくて・・・・・・」
「また野球の例えになっちゃうけど、ボールを打つことより、打席に立つことが大変なんだ、って知りましたね」
保険営業でいう「打席に立つこと」とは、「お客さんに話を聞いてもらう場を持つこと」。
「例えば、知らない人から『化粧品欲しい?』『車欲しい?』ってたずねられたら、話を聞こうと思う人はいるでしょう」
「でも、『保険欲しい?』って言われて聞く人は、ほとんどいないですよね」
「買ってもらうための場を作ることが一番難しくて、ソニー生命保険にいる間は、それができなかったんです」
2年半後に転職した生命保険会社は、「打席は準備するから、思い切ってバットを触れ」という会社だった。
「ここならやっていけるかも、と思って入社したら、数字がついてきて、自信につながりましたね」
運命的な企業
保険代理店の立ち上げも経験した後、現在のホロスプランニングに転職。
「代理店で働き始めてからは、会社が変わってもお客さんは変わってないんです。僕を信頼してくれたお客さんは、会社が変わってもついてきてくださったので」
ホロスプランニングには、運命的なものを感じている。
「実は、ソニー生命保険のOBが多いんですよ。本社が京都にあるところにも、運命を感じましたね」
社会貢献はもちろん、社員の幸せと働きがいも大切にしている。
会社の標語「あなたらしい生き方を応援します」に共感し、入社を決めた。
<<<後編 2020/03/21/Sat>>>
INDEX
05 LGBTだって悩みの中身はみんなと一緒
06 簡単かつ正確に “安心” に導く役目
07 無理して「普通」にならなくてもいい
08 悩みを抱え込まず、踏み出してほしい一歩





