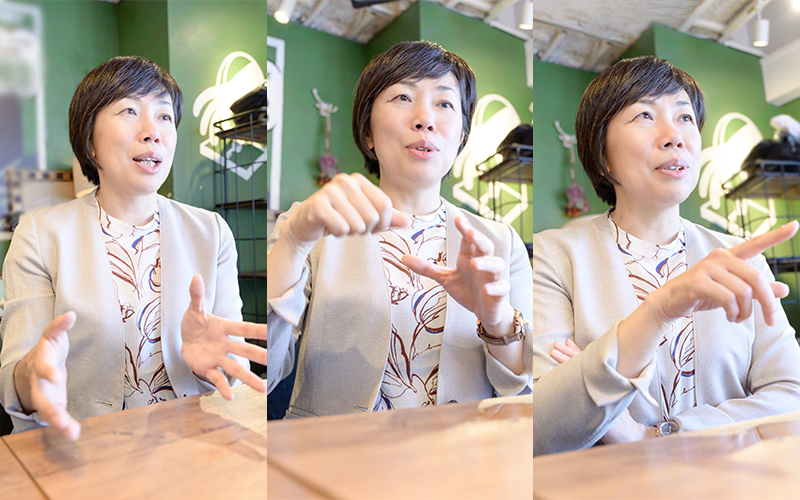02 ちやほやされるのも悪くない
03 いつも女の子を目で追いかけて
04 今でも喉が詰まる思いがする、初めてのカミングアウト
05 「レズビアン」との出会い
==================(後編)========================
06 まざまざと経験させられた「マイノリティ」
07 今につながる貴重な経験
08 職場での要らぬ苦労
09 とうとうセクシュアリティも名前もオープンに
10 世界は必ず明るくなっていく
01お茶目なお父さんが恥ずかしい
なぜ私のお父さんは、ほかのお父さんと違うの?
東京都・江戸川区で、三姉妹の末っ子として生まれる。
父は、小さな印刷所を経営していた。
「三姉妹で3つずつ年が離れているので、私が中学生に上がったとき、次女は高校生、長女は大学生で。両親は教育費を賄うのが相当大変だったと思うんですけど、当時はそんなこと、全然思い至らなかったです」
「両親には、尊敬と感謝しかないですね」
そんな父は、自営業という利点を生かし、一般企業への就職がうまくいかない知人を住み込みで雇うなど、世話焼きな一面があった。
また、ひょうきんな性格で人を笑わせることが大好きな父だった。
「保育園のお迎えに父が来ると、あのおっちゃんが来た! ってほかの園児も集まってきて。そうすると父が『よーし、見てろ!』って指が取れるようなマジックを見せて、みんなを笑わせていました」
ほかのお父さんは、9時~17時で働くサラリーマンが多いのに、私のお父さんはスーツも着ずに、朝から家にいるのが当たり前。
なんでうちのお父さんは、ほかと違うんだろう? と恥ずかしさを覚えていた。
母との距離感
おさないころ、姉たちとは仲が良いとはあまり言えなかった。
「私が小さいころに、ぜんそくを患っていて。具合が悪いときには、母が看病につきっきりだったんです。それで姉たちは『いつも、ゆりばっかり』ってやきもちを焼いてました」
「私だけピアノを習わせてもらっていたときも、家でピアノを練習し始めると、母は姉たちに『ゆりが練習するから、静かに』って言っていましたね・・・・・・」
おさないころは特に母と一緒に過ごしている時間が長かったため、母と私はよく似ていると、自分でも思う。
「今も話し方を褒めていただけることがあるんですけど、これは母譲りなんですよね。息づかいまで似ています(笑)」
母は他界したが、慕っている人が今もいることからその人望がうかがえる。
「母が亡くなってから数年経つんですけど、今でも命日に実家を訪ねてくれる方がいらっしゃいます」
「母は、相手の話をしっかり受け止めて、押しつけがましくなく的確なアドバイスをくれる人だったって、その方はおっしゃっていました」
イベントを主催してたくさんの人を集めることが好きなことの根底には、両親から受け継いだDNAも関係しているだろう。
02ちやほやされるのも悪くない
小学生のときから社交的
実家のすぐ裏にあった小学校には、下町から多くの児童が集まっていた。
「1学年150人くらい、5クラスありましたけど、どのクラスにも友だちがいましたね」
夏休みに行われるラジオ体操に参加することが楽しみだった。
「ある日、ラジオ体操に遅れまいと慌てて家を出て、学校の裏門をくぐろうとしたんです。ふと気づくと下半身にパンツしか穿いてなくて・・・・・・。急いで家に引き返したことを覚えています(苦笑)」
男女関係なく、縄跳びや野球、当時流行っていたファミコンなど、様々な遊びをする、活発な女の子だった。
学級委員に、リレーの選手も
たくさんの友人がいる小学生は、やはりクラスの中では目立つ存在となる。もちろん、学級委員を務めたこともあった。
「自薦だったか他薦だったか、学級委員になった経緯は覚えていないんですけど」
「リレーの選手になったこともありました。当時はまあ注目される方でしたね(笑)」
決して目立ちたがり屋なわけではなかったが、末っ子だったこともあり、周りにちやほやされるのは気分がよかった。
03いつも女の子を目で追いかけて
短パンを選んだだけでやっかまれる
中学校に進学し、バドミントン部に入った。
「なんでバドミントン部にしたかはあまり覚えてないんですけど、熱心に打ち込んでいましたね」
「新しいものが好きなので、中学校の制服、試合のユニフォーム、靴とかいろいろ買ってもらって、モチベーションが上がったんだと思います」
ただ、制服のスカートや部活のユニフォームで少々悩みがあった。
「男になりたいってわけじゃなかったんですけど、小学生のときはずっとズボンしか穿いてこなかったんで、スカートは本当は穿きたくなかったんです」
制服は徐々に慣れていったものの、バドミントンの試合で女性選手がよく着用している、丈の短いスカートはどうしても穿きたくなかった。
「ユニフォームのカタログを見ていたら、スカートタイプじゃなくて短パンもあって。これならいいやと」
迷わず短パンをチョイスした。でも、周りの女子部員全員が選んだのはスカート。
「なんで短パンを選んだんだ、ってちょっといじめられましたね(苦笑)」
たかが短パンを選んだだけであれこれ言われるなんて、女子って面倒だな、と感じてしまった。
気になってしょうがない後輩
やがて、部活内で意識する人が出てきた。1つ下の後輩の女子だ。
「最初は、その子が好きなんだってすぐには気づけませんでした。私は、下手な後輩を先輩として気遣ってあげているだけなのかなって」
でも、昼休みの校庭を眺めれば、大勢のなかでもすぐにその子を見つけてしまう。廊下ですれ違うだけで胸が高鳴る。
部活以外の場面でも、自分が後輩の存在を強く意識していることに気づいた。
これは恋だ。
自分の感情を受け入れた途端、不安も襲ってきた。
「女の子が女の子を好きになることは、おかしいことだって思っていたんです」
「この感情がなかったことにならないかなって、男の子を好きになる努力もしましたね」
このころから、自分は何か周りの人とは違うと思い始める。
違和感への対処に精いっぱいで、将来のことを考える余裕など持てなかった。
04今でも喉が詰まる思いがする、初めてのカミングアウト
だれかに聞いてほしい!
当時、同性愛に関する情報は乏しく、あったとしてもネガティブなものばかりだった。
「自分の違和感を説明してくれるものはないかって、学校や地域の図書館を回っても、これといったものは見つかりませんでした」
「『同性愛』って言葉は知っていたんですけど、当時の辞書で調べてみても『異常』とか『病気』とか、よくないものとして書かれていた記憶が・・・・・・」
「家に帰ってテレビをつければ、ゲイを揶揄する『保毛尾田保毛男』が出ていて・・・・・・。今思えば、なかなか辛い時期でした」
自分はよくないことをしている。
気持ち悪い。
こんなことだれにも言えない。
そう思い詰める一方で、違和感を自分のなかだけに留め続けることが限界になってきていた。
意を決してカミングアウト
苦しい胸の内を、母に打ち明けることにした。
最初にカミングアウトするなら、もっとも近しい存在である母だと決めていたのだ。
「お母さん、私、女の子が好きみたいなんだけど、って言ったのを覚えてます。口から心臓が出そうでしたね・・・・・・」
「母は、そうなんだ、大丈夫よ。心配しないで良いから、って言ってくれたんです」
否定するでも、詮索するでもなく、全面的に受け入れてくれた。
「ああ、自分は女の子が好きでも大丈夫なんだって、一気に緊張が解けました」
「このエピソードを話すたびに、今でも喉がぎゅっと詰まって、そのあとに解放されるような感覚があるんです」
しばらくあとになって、なぜあのとき、私のセクシュアリティをあっさりと受け入れてくれたのか、と母にたずねたことがあった。
「実は、母の知り合いに女性同士で暮らしている人がいて、レズビアンの当事者を知っていたんです。うちの子もそうなんだな、って思ったと言っていました」
知っているということはやはり大きいなと、改めて感じさせられた。
それとなく寄り添ってくれた父
無事に母へカミングアウトしたあと、父や姉たちには自分から伝えるからまだ黙っておいてほしい、と母に伝えていた。
でも、まだ「アウティング」という言葉もない時代。夫婦での話し合いのなかで、母は父に娘のセクシュアリティを伝えてしまっていた。
あるとき、父の部屋で見つけた本。
「両親ともに読書好きで、寝室に積ん読があったんですけど、あるとき父の本のなかにLGBTQに関するものがいくつか混ざっていて」
「それで、母に『お父さんに言ったの?』って聞いたら、『うん、言った』と。・・・・・・言うよね~、そうだよね~、って(苦笑)」
でも、娘のセクシュアリティを知って、質問したり責め立てたりするでもなく、本から知識を得て理解しようと努めてくれている父の姿勢に、私はポジティブな気持ちになれた。
パートナーを実家に連れて行ったときも、両親は歓迎ムードだった。
「パートナーとの初対面にテンションが上がりすぎた父が、いきなり立ち上がって陽気にお腹を叩いたりしてました(苦笑)」
「あとから姉二人にも伝えましたが、実にあっさりした姉たちで、あんたが幸せならいいんじゃない、というような反応でした」
一番緊張していた家族へのカミングアウトだったが、温かく受け入れてもらえたことは幸運だったと思う。
05「レズビアン」との出会い
自分と同じ「レズビアン」がこんなにいるなんて
SNSはおろか、インターネットも普及していない時代。「同性愛」という言葉は知っていても、同性愛者の女性を「レズビアン」と呼ぶことすら知らなかった。
そんなさなか、ある本に偶然出会い、衝撃を受ける。
「姉の机の引き出しを何気なく開けてみたら、1冊だけ背表紙が裏になっていてタイトルが分からない本があって。気になって取り出したら『女を愛する女たちの物語』っていう、レズビアンを特集した本だったんです」
自分と同じような「レズビアン」という人が、世の中にこんなにいるなんて! と目を皿のようにして貪り読んでいるうちに、姉が帰宅。慌てて本をもとの場所にしまった。
実は、姉の所属していた大学ゼミの教授が、オープンなレズビアンだったことが、姉がこの本を持っていた経緯だった。
「でも、後日またその本を読もうと思ったら、なぜかもう引き出しの中にはなかったんです・・・・・・。絶望しました(笑)」
「どうしてもあの本を手に入れなきゃいけない! と思って、書店のフェアに行きました」
思い切って店員に書名をたずね、無事に手に入れることができた。今でも大切に手元に残している。
このころから、サークル誌などを通じてレズビアンに関する情報を積極的に集めるようになった。
レズビアン向けのイベントにも参加
大学受験を控えていたころ、新宿二丁目で開催されたレズビアン向けのイベントに初めて参加する。
「友だちなのか恋人なのか定かではなかったですけど、とにかく自分と同じような人たちとのつながりを持ちたい一心でした」
「最初に行ったのは、レズビアンバーじゃなくてイベントでした。地下にある、ダンススタジオみたいな鏡張りの部屋に通されて、靴を脱ぐように言われて。何が始まるんだろう? ってドキドキでしたね」
イベントやお店に通ううち、出会った人たちとご飯を食べるなど、つながりができ始めた。
インターネット黎明期でもあった当時、テキストベースの掲示板に近いウェブページを通して、一緒にイベントに参加する知人も増えていった。
<<<後編 2023/10/07/Sat>>>
INDEX
06 まざまざと経験させられた「マイノリティ」
07 今につながる貴重な経験
08 職場での要らぬ苦労
09 とうとうセクシュアリティも名前もオープンに
10 世界は必ず明るくなっていく