02 黄色いランドセルの小学生
03 少しずつ生じ始める歪み
04 人を好きになるということ
05 笑顔の裏に隠した寂しさ
==================(後編)========================
06 初めて受け入れてくれた人
07 女性自衛官として生きる道
08 同期の言葉で知った「FTM」
09 変化していく自分と環境
10 自分を偽らない人生
01性別を感じなかった幼少期
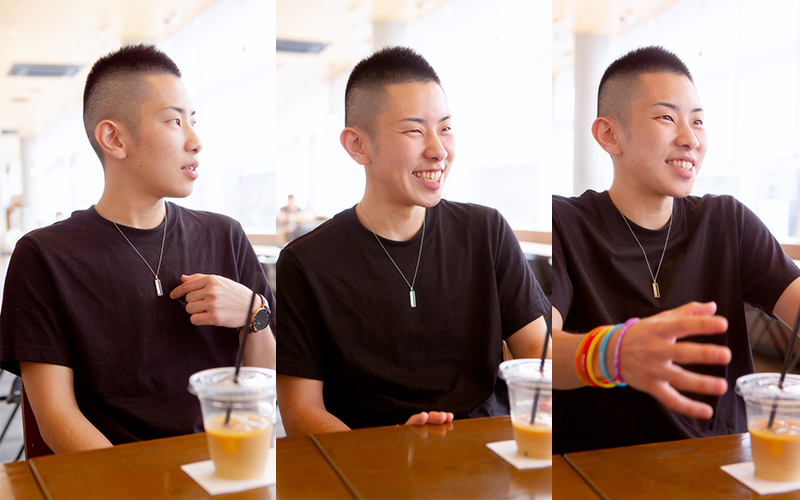
わんぱくな悪ガキ
熊本県南小国町で育った。
自然に囲まれた温泉街だ。
「最初の仕事で離れたことがある以外は、ずっと熊本にいます」
「熊本といえば、火山、カルデラ、熊本城にくまもんかな」
「地元は、お隣さんといっても家同士が遠いような場所で、移動手段は車かバイクですね」
一番古い記憶は、保育園の頃。
2歳の時に両親が離婚し、母の実家がある南小国に引っ越した。
「引っ越した家の近所に、同い年の悪ガキがいたんですよ」
「男の子だったんですけど、一気に意気投合した記憶があります」
「よく2人で、保育園の園長先生のスカートをめくってました(笑)」
「叱られても続けるくらいには、わんぱくでしたね」
悪ガキの幼なじみとか、小学校から高校まで、学校だけでなくクラスもずっと一緒だった。
「実は、最初の職場も同じだったんです(笑)」
「腐れ縁の悪友、いや、戦友ですね」
全校生徒24人の小学校
外に出て、パワフルに遊ぶ子どもだった。
「裸になって川に入ったり、道端になってる野イチゴを食べたり」
「野生児でした(笑)」
地元は子どもが少なかったため、年齢も性別も関係なく、みんなで遊んでいた。
「小学校もちっちゃくて、全校生徒で24人しかいなかったんですよ」
「僕の学年は8人いて、男の子が2人、女の子が6人でした」
「だから、男とか女とか感じさせる環境じゃなくて、友だちというより兄弟みたいな関係でしたね」
「みんなわんぱくで、グラウンドでドッジボールしてました」
「デュエル・マスターズってカードゲームとかビーダマン、ミニ四駆も、みんなで遊んでたな・・・・・・」
「いじめとかはなくて、全員でワイワイしている感じでした」
02黄色いランドセルの小学生
ちっちゃいヤンキー
小学生の自分は、とにかくわんぱくだった。
低学年の頃は気性が荒く、叱られるたびに、先生に反抗していた。
「ちっちゃいヤンキーでしたね」
当時、苦手だったものは牛乳。
給食で出た牛乳をストーブの裏や戸棚の奥に隠していた。
時間が経って腐った牛乳が出てくるたびに、先生に怒られた。
「怒られるのが嫌になって、一度、学校を飛び出したことがあるんですよ」
「温泉目当ての観光客がいっぱいいる中を、昼過ぎくらいに1人で帰ったんです」
「そうしたら、知らない人に話しかけられたんです」
最初は不審者だと思い、逃げようとしたが、話を聞くと雑誌の取材で来ているようだった。
「どうしたの?」と聞かれ、「先生とケンカして飛び出しました」と答えた。
「その様子が “黒川温泉で出会った小学生” って『じゃらん』に載ったらしいんです」
「親戚中から『あんた、バカじゃないの』って爆笑されましたね(笑)」
“僕” という意識
小学生の頃、当時では珍しい黄色のランドセルを背負っていた。
「ピカチュウになるのが夢だったんです(笑)」
「ばあちゃんに『ピカチュウが好きだけん、ランドセルは黄色がいい』ってねだって、買ってもらいました」
ショートヘアでズボンをはいていた自分を、雑誌の編集者も男の子だと思ったかもしれない。
「観光客から、『ぼく、道教えて』とか『Boy!』って声をかけられることが普通でした」
「性別を意識したことはなかったけど、自分のことは “僕” だと思ってました」
ときどき、観光客から「お嬢さん」と呼ばれると、「なんでバレたんだ?」と驚いた。
「『志麻ちゃん』とか『お嬢ちゃん』って呼ばれるのは、嫌でしたね」
「ばあちゃんから『フリフリを着なさい』『髪を伸ばしなさい』って言われるのも面倒でした」
口を出された時は、「ごめん、着れない」「髪は短くするけん」と断っていた。
一度だけ、スカートをはいた記憶がある。
小学校の入学式の日。
「ばあちゃんが入学式のために、服を用意してくれたんです」
「いつもすごく良くしてくれるから、ばあちゃんを悲しませたくないと思ったんですよね」
それ以来、スカートをはくことを拒み続けた。
「はかせようとすると僕がうるさく抵抗するから、親もばあちゃんもはかせなくなりました」
03少しずつ生じ始める歪み

兄弟みたいな寮生活
中学校は、自宅から10kmほど離れていた。
「一番近い中学がそこで、3つくらいの小学校から生徒が集まるんですよ」
「遠くて通えないから、寮で3年間過ごしました」
「保育園から一緒の同級生も先輩も後輩も寮に入ったから、兄弟と住んでいるみたいでした」
寮の中では、男子部屋と女子部屋のエリアが分かれていた。
しかし、消灯前であれば自由に行き来できたため、ここでも性別を意識することはなかった。
「エリアの間にロックがかかってるわけじゃないから、『漫画貸して』って男子部屋に行ってましたね」
「食堂は1つだったから、ご飯もみんなで食べていました」
女友だちとのお風呂
“僕” という意識はあったが、女の子と一緒にお風呂に入ることに抵抗はなかった。
「地元が温泉街だから、家にお風呂がなくて、毎日共同浴場に行っていたんですよ」
知らない人とお風呂に入ることが日常だったため、寮でも特別な感覚はなかった。
「体を洗わなければいけないから、普通にお風呂に入ろうって感覚で、ドキドキはしなかったですね」
「むしろ寮は、同じ地区で育った人たちしかいないから、家族とお風呂に入る感覚でした」
小さい頃から一緒に裸で川遊びをしていた子たちだから、何とも思わなかった。
止められない体の変化
中学校では、同じ小学校だった女子たちと一緒にいることが多かった。
「保育園から一緒だから、女の子のグループにいるって意識はなかったんです」
幼なじみの悪ガキとは、中学生になってから話さなくなる時期があった。
「一緒にいると、『つき合ってんの?』とか言われることもありました」
「お互いに『まさかこいつと?(笑)』って感じだったから、長くいじられることはなかったけど」
中学に進学しても、特に性別を意識することはない日々が続くはずだった。
「やっぱり、なんで制服のスカートをはかなきゃいけないのかが、疑問でした」
「ジャージ登校は禁止で、冬は黒タイツをはかなきゃいけなかったんです(苦笑)」
「スカートの下に短パンをはいて、気を紛らわせるぐらいしかできなかった」
そして、体も徐々に女性らしくなっていく。
「二次性徴が始まったのは、嫌でしたね」
「ブラジャーを買いに行くのも嫌だったし、そもそもいらないんじゃないかって」
「小学校からバレーボールを続けていたから、スポブラでしのいでました」
今振り返ると、中学時代が一番違和感を抱いていたかもしれない。
04人を好きになるということ
素直に表せた好意
時はさかのぼり、小学1年生の時、初恋をした。
相手は女子だった。
「本当に好きで、何の抵抗もなかったです」
「人を好きになることは普通だから、隠さないでいいや、って思ってましたね」
「そもそも自分を女性だと思ってないから、女の子を好きになっていいじゃん、って」
「好き」という気持ちを、素直に表現した。
「相手に『好きやけんねぇ』って話したり、アプローチしたりしてました(笑)」
自分は同性愛者?
中学に上がると、別の小学校から来た同級生の間で「女子好きな女の子がいる」とウワサになった。
「小学生の頃のままで、女の子に対する恋愛感情を隠していなかったんですよね」
「周りから、『なんでそんなに堂々としてるの?』って思われていたみたいです」
「先輩や同級生の男の子から、『レズやん』って言われるようになりました」
この時に初めて、自分自身が同性愛者なのかもしれないということに気づいた。
「僕は女性じゃないのに、なんでかな・・・・・・って、自分でも不思議に思うことがありました」
ただ「レズ」と言われるだけで、周りに避けられることはなかった。
ケンカに発展することもなかった。
好意を抱いた相手には、変わらずに「ドキドキするけん、恋かな?」と伝えた。
時には「気持ち悪い」と、拒否されることもあった。
「両想いになったことはなくて、拒否されるより、取り合ってもらえないことの方が多かったです」
「女の子たちは、普通の友だちのノリで受け取っていたんだと思います」
「自分がおかしいのかな、って思ったこともあったけど、好きやけん仕方ないなって感じでしたね」
男子を好きになる努力
休日、寮から実家に帰った時も、「あの子が好きでさ」と自然と話していた。
母親に「あんた、女の子が好きなの?」と心配される。
「同級生の男の子の中に、お母さんが気に入っていた子がいたんですよね」
「その子の名前を上げて、『この子がいいんじゃない?』って、お母さんにアドバイスされました」
「もしつき合ったら、お母さんは喜ぶのかな、って好きになる努力をしたんですよ」
その男子を目で追い、隣に座り、話しかけてみた。
意識すればするほど、話が盛り上がらなかった。
女子に感じたようなドキドキが、こみ上げてくることもなかった。
「・・・・・・やっぱり何かが違ったんです」
「男の子を好きになろうとしている時間が、無駄だと思えてしまったんですよね」
05笑顔の裏に隠した寂しさ

父親の暴力
2歳で両親が離婚してからは、母親と2人きりの生活が続いた。
小学2年生の時、突然見知らぬ男性が現れた。
小学4年生の時、弟が生まれた。
「僕も小さかったから詳しく覚えてないけど、気づいたら再婚していたと思います」
今の父親のことは、今でもあまり受け入れられていない。
「外面はすごくいいんですけど、昔はいきなりプツンと切れて、暴力を振るうことがあったんです」
怒り始めた理由は覚えていないが、一度首を絞められたことがあった。
息が止まりかけ、必死に抵抗し、「殺す気があるなら包丁でも持ってこい!」と挑発した。
父親は、台所に向かった。
「そこでようやく、料理をしていたお母さんが止めてくれたんですけど・・・・・・」
「茶碗を投げられた時もあって、小さかった弟が泣き叫んで、止まりました」
母親の愛情
中学の寮は週末に閉まってしまうため、毎週金曜に実家に帰っていた。
その頃、母親は10歳下の弟につきっきりだった。
「『金曜日に迎えに来てください』ってお母さんに連絡すると、『帰ってくんの?』って感じなんですよ」
「だから、自分はいらない子なんだろうな・・・・・・みたいに思えてしまって」
「体が女性っぽくなり始めてた時だったから、その嫌だった気持ちと合わさって、不安定になりましたね」
「親に隠れて、手首を切ったりもしました」
自分には親の愛情が向いていない、と感じた。
週末は家にいたくなかったため、祖母が営む旅館を手伝いに行っていた。
「旅館に行くと、親戚や従業員のみんなにかわいがってもらえたから」
「夏休みの時も、親戚の家で1カ月過ごしてました」
「お母さんは、ばあちゃんや親せきと仲が悪かったんですよ」
「だから、ばあちゃんたちと仲がいい僕が、嫌だったのかな」
本音はわからないが、母親は「志麻ばっかりひいきされて」という気持ちを抱いていたのかもしれない。
母親だけが弾かれているように、感じてしまったのかもしれない。
「それでも、僕が『ばあちゃんのとこに行かない』っていうと、お母さんは怒るんですよ」
「これも推測だけど、お母さんとおばあちゃんをつなぐものが僕しかなかったから、行かせていたんだと思います」
「今だから感じることだけど、お母さんは不器用なんですよね」
不安定な精神
二次性徴が始まり、自分の性別を意識し始めると同時に、家族関係が悪化した。
精神的に不安定になり、徐々にわんぱくさは影を潜めていった。
「小学生の頃は、軽く小突いて相手の気を引かせれば、仲良くなれたんですよ」
「でも、中学生になると『あいつはすぐ暴力を振るってくる』って言われたんです」
友だちになりたいから、ちょっかいを出すのだが、逆に離れていってしまう。
「みんながみんな、わんぱくじゃないんだなって、思い知らされました」
しかし、心の中のモヤモヤを、友だちにはなかなか相談できなかった。
友だちに心配させたくなかった。
学校のことも家族のことも言えなかった。
「だから、学校にいる自分と家にいる自分は別人みたいで、二重人格みたいだったと思います」
ただ一度だけ、友だちに本音を言わざるを得ないことがあった。
バレーボールの試合の前日に父親に暴力を振るわれ、あざを作ったことがある。
このままでは、試合に出られなくなると危機感を抱いた。
「その時は、友だちに事情を話して、家に泊めてもらいました」
力になってくれる存在がいたから、精神が崩壊してしまうことは防げた。
<<<後編 2018/08/05/Sun>>>
INDEX
06 初めて受け入れてくれた人
07 女性自衛官として生きる道
08 同期の言葉で知った「FTM」
09 変化していく自分と環境
10 自分を偽らない人生





