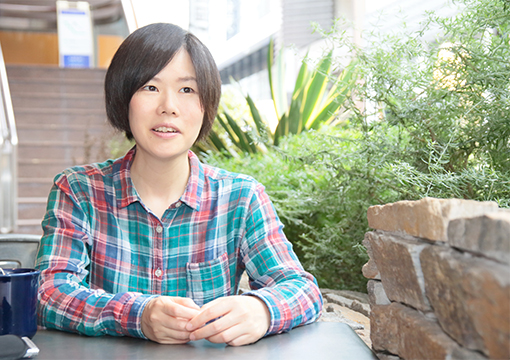02 自由にさせてくれる優しい両親
03 一人で過ごす大人しい子
04 お父さんがコーチの地元野球部に参加
05 アニメの声優を志して養成学校に入門
==================(後編)========================
06 アマチュア劇団で役者として舞台に立つ
07 卒業式の直前にカミングアウト&告白
08 タイプの人は年上のショートカット
09 彼女を作って、結婚式を挙げたい
10 メンタルヘルスのカウンセラーを目指す
01検索でたどり着いたXジェンダーという言葉
深まる男女分けの違和感
小学生のころまではセクシュアリティについて考えることはなかった。
「習っていた野球の関係で髪はショートでしたけど、ただ、ちょっとボーイッシュな女の子でした」
違和感を感じ始めたのは、中1のとき。男女分けの場面に接すると、居心地の悪さを覚えるようになった
「女子はこっち、男子はこっち、と分けられるたびに、『えーっ。なんか違う』と感じました」
「女」として扱われたくない。「女」じゃない。だんだん、そう強く感じるようになった。
「でも、男のグループに入りたい、男になりたいというわけではありませんでした」
Eテレの「バリバラ〜障害者バラエティ」を小学生のころから見ていて、「性同一性障害」という言葉は知っていた。
「でも、自分は性同一性障害ではない、って思ってました」
セクシュアリティに関する違和感を覚えてからは、番組に対する興味も深くなっていく。
自分のことを「ぼく」というようになったのも、このころだ。
「自然に出た感じですかね。今は、『ぼく』と名前が半々です。『私』は、ほとんど使いません」
「ぼく」と呼ぶに関して、家族から否定されたこともない。
Xジェンダーにたどり着く
中2までは、違和感を感じつつも、性別やセクシュアリティを疑問に思うこともなかった。
「分からないままにしていたので、それが悩みのピークでした。『学校、行きたくねー』と思ったこともありましたよ」
自分は何なんだろう? 答えが欲しくて、次第にネットで検索するようになる。
「Googleで調べ、Twitterで調べ、YouTubeで調べました」
入力したキーワードは、「男女、どっちでもない」「性別が分からない」など。
「最初に出てきたのは、LGBTでした」
聞いたことがある単語だった。もっと調べると、ジェンダーレスという言葉が出てきた。
「ジェンダーレスは、ファッションに関する用語だと知ってたので、これは違うな、と・・・・・・」
「パンセクシュアルも、違うな・・・・・・」
そして、ついに「Xジェンダー」という言葉にたどり着く。
最初は、Xジェンダーを自称する「ユーチューバーぺさ」さんの投稿だった。
「こういう感じの人もいるんだな、と思って見ているうちに、あ、これ、ぼくに近いかも、と感じ始めました」
恋愛対象は男性ではない
さらに検索を続け、Xジェンダーを自認するようになる。15歳のときだった。
「男でも女でもない。中間、中性という感じです」
「XジェンダーかFTXか、細かい部分で迷いはありますけど、一応、性自認できました」
恋愛対象は、「男性以外」だと今は思っている。
「トラウマがあるわけではないし、男性恐怖症でもありません。理由は分からないんですけど、男じゃないな、と」
「あの男優、カッコいいよね」などと、友だちからいわれても、「は?」と答えるしかない。
「まったく興味が沸かないし、ましてや恋愛対象として考えられないんです」
未知数のところはある。
「これから、分かっていくことも多いと思います」
02自由にさせてくれる優しい両親
お母さんは新聞配達
千葉県松戸市で生まれ育った。4歳年下の弟がいる。
「弟は、中学2年生です。半分、ゲーム依存(苦笑)。ご飯のとき以外は、ずーっとゲームをしています」
お母さんは、新聞配達のパートをして家計を助けている。
「ぼくが幼稚園のころから新聞配達を始めました」
朝刊を配るために、午前1時にバイクに跨って家を出ていく。
雨の日も風の日も休むわけにはいかない。
「雨の日はカッパを着ていきます。あんまり天気が悪い日は、バイクが滑って事故を起こさないか、心配になりますね」
「帰ってくるのは、午前5時ごろ。それから、お風呂に入って、朝ごはんの準備をしてくれます」
洗い物を済ませると、すぐに寝てしまう。
「寝ないと、死んじゃうんで(笑)」
夕刊の配達は、午後1時から。ほぼ、毎日、仕事はある。
「日曜と祝日は、家事だけして、寝転んでグータラしています」
「お母さんもゲームが好きなんで、スマホゲームをしていますね。内面はズボラですけど、顔は美人です(笑)」
LGBTERに出ることも認めてくれた
子どものころから、「悪いことじゃなければ、なんでも許すから。悪いことだけは、手を出さないで」といわれてきた。
悪いこととは、先生に呼び出されたり、警察のお世話になったりすることだ。
「だから、口うるさく、いろいろ干渉されることもなかったですね」
気に障る小言をいわれることもなく、とても居心地がいい家庭だった。
LGBTERのインタビューを受けることが決まったと話しても、不安そうな顔はしなかった。
「どんなことを聞かれるんだろうね、とは言っていましたけど」
サイトを見せると、「へー、こんな感じなんだ」と納得した様子。
顔を出すことも、何もいわずに許してくれた。
「信用してくれているのか、何をしても反対されることは、ほとんどありません」
お父さんはゴルフの「レッスンプロ」
お父さんは身長186センチの長身。ゴルフのレッスンプロをしている。
「夜の時間帯のレッスンもあるので、帰りが遅い日が多いですね」
礼儀などには厳しかったが、お母さんと同じように、基本的には自由にさせてくれる。
「たまに、絶対にやらなくちゃいけないときだけ、早くやれ! とかいわれます。たとえば、宿題とか」
お父さんとケンカをしたこともない。
そんな物わかりがいい両親なのに、弟はよく言い合いをしている。
「くっだらないことで、すぐケンカになるんですよ。反抗期なんですかね(笑)」
弟はお父さんに似て、体格がいい。中2で180センチ近くもある。中学では剣道部に入っている。
「弟はゲームばっかりしているから、最近はあまり話す時間がありません」
03一人で過ごす大人しい子
元気いっぱいの友だち
幼稚園のころは、家の中で遊ぶのと外で遊ぶのが半々くらいだった。
「家の中で遊ぶときは、ぬいぐるみで遊んだりしていました。外で遊ぶときは球技系とか、鬼ごっことかですかね」
外で遊ぶのも珍しくない、そこそこ活発な子どもだった。
「近所に一人、仲のいい女の子がいたんです。元気がありあまっているような子でした」
いつもはしゃいでいる、いい意味で落ち着きがない子だった。
「ぼくは正反対で、普段はおとなしいタイプでした。外で遊ぶときは思い切り、はしゃぎましたけど」
家の中でも外でも、遊ぶときはその友だちと一緒だった。
“ぼっち” でいるのが気持ちいい
小学校に入ると、すぐに引きこもってしまった。
「なんだか、学校に馴染めなくて」。それでも、3、4週間で克服して、通学できるようになった。
「そのあとは、体調が悪くて休むことはときどきありましたけど、登校拒否とかはありませんでした」
しかし、クラスでは、好んで “ぼっち” だった。
「2、3人は話をする子がいましたから、それ以上、友だちはいなくてもいいや、と。一人のほうが楽だし、という感じでしたね」
教室の隅で絵を書いたり、本を読んだり、静かにしていることが多かった。
「クラスに溶け込みたいとも思わなかったし、寂しいと感じたこともありませんでした」
みんなが楽しそうに遊んでいるのを見て、うらやましいとか、仲間に入りたいとも思わない。
「からかわれたり、いじめられたりもありませんでした。ただ、大人しい子と思われていたんでしょうね」
学校の成績はきわめてフツー
勉強もごく普通の成績だった。
「苦手な科目もあったけど、フツーに授業に出て、フツーの成績を収めて、フツーにやってました」
通信簿に、「宿題はちゃんとやりましょうね」と書かれたことがある。
「やりたくねーや、と思って、“わざと” 忘れることもありましたね。でも、週に1回くらいでしたから、まあ、まあ」
ときどき、絶対にやりたくねー、と思うこともあった。それでも大きな問題になることはなく、学校生活は普通に過ぎてく。
04お父さんがコーチの地元野球部に参加
チーム史上一人だけの女子選手
小学校4年生のときに、地域の野球チームに入った。
「お父さんがコーチをしていて、『お前も野球でもやって、体を動かせ』という感じでしたね」
「あのころは趣味もなかったので、まあ、やってみようかな、と」
その後、弟も同じチームに入部した。家族が一緒にいることで、楽しく練習をすることができた。
小学校2年生から5年生までのチーム。男女混合だったが、女の子は一人だけだった。
「チーム史上、一人きりの女子かもしれませんね」
男子ばかりに混じって練習をすることにも抵抗はなかった。
主に外野、ときどき内野を守る。
「試合ではベンチにいることも多くて、助っ人的に出場していました」
土、日の練習は休まずに参加した。野球をやっていて、唯一、困ったのが日焼けだ。
「日に焼けたくなくて、夏でもずっと長袖を着ていました。一番、すごいときは、日焼け止めを1日に6本も使ってました(笑)」
結局、特別に中学2年までチームに在籍した。
ハーレムもののライトノベル
小学校5年生のときに出会ったのが、ライトノベルなどの小学校高学年向けの文庫本だった。
「子どもなのに、これかーって思われそうですけど、好きだったのは、ハーレムものですね(笑)」
ハーレムものとは、一人の男子の主人公に複数の女の子が集まってくるタイプの話だ。
「自分を主人公にオーバーラップさせてました」
女の子たちにモテる自分を想像し、そのキャラクターを使って、自分なりの小説を書き進める二次創作にもハマる。
「教室で、一人で小説を書いたりしていることもありました」
05アニメの声優を志して養成学校に入門
現実の厳しさを知る
小学校の高学年からアニメが好きになり、その趣味は今でも続いている。
「小学校6年生のときに、アニメの声優を目指そうと思い立ちました」
調べてみると、柏に声優の養成学校があることが分かった。
「中学3年生までが通う、ジュニアクラスに通い始めました」
発声練習のほか、しっかりと声を出すための筋肉トレーニングやストレッチのレッスンもあった。
「こんなに体力が必要なのかと知って、びっくりしました」
背筋を伸ばし、ハキハキと滑舌よく話すためには、それなりに体力が要求されるのだった。
「現実を見て、無理かなと思いました。走るのとか、運動がとにかく嫌いでしたから・・・・・」
中学1年生まで、2年間ほど通ったが、アニメ声優になる夢は諦めることにした。
演劇にチャレンジ
中学では、特に部活には入らなかった。
「部活をやれば内申書が良くなると聞いていましたけど、面倒だったんでやめました」
部活に入らない代わりに、有志による演劇に参加する。
「卒業式の前に『3年生を送る会』があって、そこで在校生が演劇を披露するんです。それに自分で応募しました」
アニメやライトノベルに通じるものを感じ、やってみたいな、と思った。
「2年生のときは、主役とはいわないまでも、セリフの多い役を演じました」
2年間、声優養成学校で習った発声が生きたのかもしれない。舞台で演じることに心地よさを感じた。
「プロの声優は諦めましたけど、趣味でやっていくのはいいかな、と思って、劇団を探したんです」
すると、地元で活動をするアマチュア劇団が見つかる。さっそくその門を叩くことにした。
<<<後編 2020/11/02/Mon>>>
INDEX
06 アマチュア劇団で役者として舞台に立つ
07 卒業式の直前にカミングアウト&告白
08 タイプの人は年上のショートカット
09 彼女を作って、結婚式を挙げたい
10 メンタルヘルスのカウンセラーを目指す