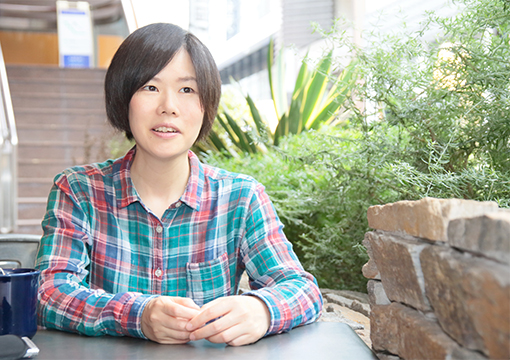02 女の子のそばが安心
03 父との距離
04 世の中ってそういうもの
05 進路を決める
==================(後編)========================
06 恋愛ってどこがおもしろいの?
07 それでも家族
08 Xジェンダーへの共感
09 最初に話すべき人
10 同世代へのエール
01穏やかな子ども時代

プールの思い出
栃木県足利市で生まれ育った。
かつての城下町で、今も古い町並みが残る。
家の近所には山があり、子どもの頃は父と一緒に、犬の散歩ついでに山を登った。
寡黙な子どもだったため、母はずいぶん心配した。
「1人遊びが好きだったんです」
「長いことしゃべらずに、くまちゃんのぬいぐるみを傍らに置いて、黙々と遊んでいたとか(苦笑)」
「心の病を患っているのかもしれない・・・・・・。そんな風に思っていたと、母に聞きました」
父は男子高の体育教師。
幼稚園や小学校の夏休みには、父が勤めていた高校に頻繁に連れて行かれた。
「夏休み中って、生徒がプールに入らないじゃないですか。父は『泳ぎを教えてやる』と連れて行って、私と姉をプールに投げ飛ばすんですよ」
高校生用のプールは深く、溺れないように手足をバタバタ動かした。
父はプールの中で仁王立ちして、そんな娘たちの様子を見ている。
「子どもの頃を思い出そうとすると、あのときの恐怖感がジワジワよみがえってきます(笑)」
「その特訓のおかげで、泳げるようになったんですけどね」
父はマイペースな人で、少し変わり者だった。
「高校のプールの傍にある小さなスペースで、ナスやトマトを勝手に栽培するような人でした」
「実った野菜を収穫して、『学校で作ったやつだよ』って、よく家に持ち帰ってきたんです」
「今同じことをすれば、きっと問題になりますよね(笑)。自由な時代だったんだなと思います」
過保護な母
6歳上の姉がいるが、姉妹というより、もう一人のお母さんという印象だった。
「子どもの頃は、姉がすごく大人に見えてました」
「一緒に遊ぶというよりは、かわいがってもらっていた感じです」
姉とのあいだには、2歳上の兄がいたはずだった。しかし、自分が産まれる前に事故で亡くなったと聞いた。
「『お母さんは過保護が過ぎたよね』って、姉はよく言うんです」
「兄を亡くしているぶん、どこへ行くときも母がついてきたし、何をするときも心配されました」
「私自身は、愛情を持って育ててもらったという実感があるけど、姉からは過保護に見えてたみたいですね」
02女の子のそばが安心
黄色い幼稚園バッグ
好きな服装や好きな色は、子どもの頃から変わらない。
幼稚園バッグを選ぶときも、真っ先に青を選んだ。
「ピンクと青と黄色の3色から好きな色を選べたんです」
「女の子はたいていピンクを選ぶけど、私は青が欲しかった」
「だから、『ピンクでいい?』って母から聞かれたときに、『嫌だ。青がいい』って答えたんですよ」
母が最終的に買ってくれたのは、黄色いバッグだった。
「青が良かったな・・・・・・」
心の中でそう思いながら、なぜか強く主張できなかった。
幼稚園が始まると、ほとんどの子がピンクか青のバッグを提げていた。黄色いバッグの子は少数だったから、目立つようで恥ずかしかった。
幼稚園では女の子とも男の子とも分け隔てなく遊ぶ。
でも正直なところ、女の子といるほうが、ずっと居心地がいいと感じていた。
「男の子と一緒にいると、マウンティングされているような気持ちになったんです」
「相手の男の子には、そういうつもりは全くないと思うんですけど・・・・・・」
「もしかしたら、男の子に対して、ライバル心みたいなものがあったのかもしれないですね」
女の子だけのソフトボールチーム
小1のときに、学級委員長などリーダー的な役割を任された。
それがきっかけで、生来の責任感の強さに火がつく。幼稚園のときとは打って変わって活発になった。
「勉強もスポーツも嫌いじゃなかったので、一生懸命やりました。いま振り返ると、バランス良く何でもこなせるいい子だったと思います」
ソフトボールのチームに入ったのは、小4のとき。
「小3の終わりに、体育の先生が教室を回ってきて、『女の子だけでソフトボールチームを作るけど、やりたい子?』って呼び掛けたんです」
「ソフトボールのルールは知らなかったけど、なんだかワクワクしました」
「友だちと一緒に、元気よく『はーい!』って手を挙げましたね(笑)」
楽しそうという理由だけで始めたが、ソフトボールの練習はかなりハードだった。
疲れてヘトヘトになっても「水を飲むな」という当時のスパルタ指導。
土日も当たり前に練習や試合があった。
「体が大きいほうだったので、試合ではキャッチャーをやらせてもらうことが多かったですね」
「ボールを伸びやかに投げられる点を買われて、外野を任されることもありました」
03父との距離

理不尽な言いがかり
特別な悩みもないまま小学校を卒業し、中学生になる。
しかし、思春期に差しかかった頃から、父への反発心が強くなっていった。
「母はもともと小料理屋の娘で、自分もそういうお店を開きたいという願望があったようです」
「私が中学生になると同時に、小料理屋の女将として働くようになりました」
「姉は東京の短大に通うために家を出たので、家に父と私の2人きりのことが多くて・・・・・・」
「父との距離感に戸惑って、訳もなくイライラすることが多くなりましたね」
父はお酒が好きで、夕食後にたびたび晩酌をした。
今なら「一緒に飲む?」と言えるかもしれない。
しかし当時は、アルコールで陽気になったり、声が大きくなったりする父のことがさっぱり理解できなかった。
「うるさいんだけど」と強い口調で文句を言うと、口論になる。
「家にいたくなかったですね」
「かといって、行くところもないから、ずっと部屋に閉じこもってました」
父に反発してケンカになると、母はいつも父をかばう。
「お父さんは、秀ちゃんのこと色々考えてるんだから・・・・・・」
そうなだめられることで、父への反発がより一層強まった。
自分だけが空回りしているようで虚しかった。
「今考えると、父は一度も高圧的な態度を取らなかったんですよ」
「娘の理不尽な言いがかりに対して、よく何も言わなかったな、と思います」
何にあんなに怒りを燃やしていたのか、自分でもわからない。
「生理が始まっていたし、体つきも変わりつつありました。そういうことに対する違和感みたいなものが、怒りの燃料だったのかもしれませんね」
「親への反抗というよりも、自分の寄るべなさに反発していたのかもしれません」
音楽だけが拠り所だった
典型的な「いい子」だった小学生時代から一変、中学生になると、勉強を一切しなくなった。
成績はどんどん落ち、自暴自棄になっていく。
「周りに信頼できる大人がいなくて、苦しかったです。特に、中1のときの担任の先生のことは毛嫌いしてました」
担任の先生は、当時28歳くらいの若い男性で、バスケ部の顧問をしていた。
バスケ部員など、自分に懐いている生徒へのひいきが激しく、そういう大人の姿を見るのがたまらなく嫌だった。
学校生活に楽しみを見い出せず、何もかもが面倒くさくて、部活も辞めてしまう。
「ひたすら音楽に没頭してました」
「(松田)聖子ちゃんが大好きで、お小遣いを貯めてはレコードを買って、ずっと聞いてましたね」
武道館のコンサートに行きたいと母にねだってみたものの、1人で行くのはダメと言われた。
「どうしても行きたいから、もう必死です(笑)」
「東京で1人暮らしをしていた姉に頼み込んで、一緒に行ってもらいました」
「武道館には2回行きましたね。憧れの聖子ちゃんを生で見て、すごく感動したことを覚えてます」
04世の中ってそういうもの
時間が解決してくれる
自分の体にはずっと違和感があった。しかし、「いつか治るはず」と客観的に捉えるようにしていた。
「今よりもっと大人になって、好きな人ができれば、この違和感はなくなると思ってました」
「なんかおかしいな? と感じることはあったんですけど、くすぐったいくらいの感覚」
「きっと時間が解決してくれる、って信じてましたね。世の中はそういうものなんだと、自分に言い聞かせてたんです」
中学生時代、性的な話題に対しては、潔癖で神経質だった。
「当時は『平凡パンチ』や『明星』などの雑誌に、セクシーなグラビアが載ってたんですよ」
「すごく嫌でしたね。気持ち悪いって感じ。男の子が性的な話で盛り上がってるのも嫌でした」
恋愛にも興味はなく、話題を振られても乗ることはなかった。
おしゃれに目覚める
中学卒業後は女子高に進学。
比較対象の男の子がいない環境は居心地が良く、のびのびと過ごせた。
アイドルへの熱は次第に冷めて、おしゃれやトレンドへの関心が加速していく。
「DCブランドが溢れていた時代で、バイトをしては洋服を買ってました」
「バイトは校則で禁止されてたけど、学校には内緒で、マックとかで働いてましたね」
制服のある高校だったため、私服を着る時間はあまりない。
それでも、せっせとバイトをしては、クローゼットに新しい服を増やした。
「服を着たいというよりも、ショップのお姉さんやお兄さんと話すのが楽しかったんです。ちょっとだけ大人になった気分でした(笑)」
「プライベートが充実していて、忙しかったから、セクシュアリティに悩む暇もありませんでしたね」
「高校時代は、毎日楽しかったです」
05進路を決める

父との和解
中高時代、ひそかに憧れていた職業はラジオDJだ。
深夜ラジオが好きで、よく聞いていた。顔を見せずに、声や話ぶりだけで人を引きつけるDJはすごいと思った。
「そういう仕事って、教養が必要じゃないですか」
「将来の進路を本格的に考え始めたときに、自分はラジオDJにはなれないって悟ってしまったんです」
「勉強せずに遊びほうけていたことを、初めて後悔しましたね(苦笑)」
父は教師だし、娘には大学に進学してほしいと思っているだろう。
関係は相変わらずぎくしゃくしていたが、「大学に進学したほうがいい?」と思い切って相談してみた。
「そんなこと気にする必要ないから、自分のやりたいことをやれ」
父はそう言って、数日後にある専門学校のパンフレットをもらってきてくれた。
「お父さんは、秀ちゃんのこと色々考えてるんだから・・・・・・」
母からよく言われたその言葉を、初めて理解できた気がした。
「父が渡してくれたのは、フィットネスやエアロビスクのインストラクターを養成する専門学校のパンフレットでした」
「せっかく父が勧めてくれたし、その専門学校に進学することを決めたんです」
「19歳のときに上京して、大井町にあった専門学校に2年間通いました」
東京から地元へ
当時は、フィットネスやエアロビクスの隆盛期。
インストラクターの就職口がありすぎて、選り取りみどりの時代だった。
「専門学校卒業後は、スポーツクラブに就職しました」
3年ほど、東京でインストラクターとして働いた。
しかしあるとき、父が軽い脳梗塞を起こしたと連絡が入る。
「家族の中で、そういうことが初めて起きたので、母も姉も私も動揺しました」
「それまで、本当に元気で健康な父だったので、余計に心配でしたね」
「東京の生活に疲れてきたこともあって、父の看病をするために、一度地元に帰ることを決めました」
あのとき地元に帰ったことが、自分の人生を決めたといってもいいかもしれない。
地元で見つけた転職先で、後に夫となるパートナーに出会ったからだ。
<<<後編 2020/04/11/Sat>>>
INDEX
06 恋愛ってどこがおもしろいの?
07 それでも家族
08 Xジェンダーへの共感
09 最初に話すべき人
10 同世代へのエール