02 人生を決めた障碍者施設のボランティア
03 吹っ切れて、カミングアウトラッシュ
04 あなたを産まなければよかった
05 カミングアウトのリスク
==================(後編)========================
06 マイノリティが生きやすい社会を
07 性的マイノリティのメンタルヘルス
08 同性カップルで暮らす難しさ
09 あと10年で夫夫の銀婚式を
10 人が変われば、世間も変わるはず
06マイノリティが生きやすい社会を
障碍者教育の現場の不安定さ
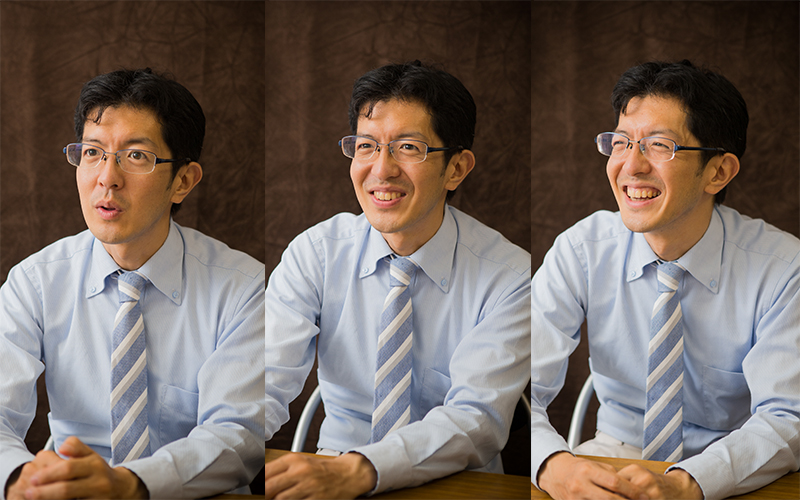
「僕は私立の養護学校に教員として勤めていたんですが、長く勤めるのが難しい環境で。職員の入れ替わりが激しいんですよ。ある程度の年齢にいってしまうと、たとえば体をこわしてしまったら勤続できないとか。勤めていた学校の校長先生は非常勤でしたし、教頭先生は給料の何割かを自主的に返納していたんです。職員を安定して雇う体力がない。これは、様々な保育施設や服施設でも同様。公立であれば可能なことが、私立では難しいのもおかしな話だと思ったんです」
支える手が必要な障碍のある子どもの教育に従事している人が、ちゃんと生活していけるような労働環境や保障制度を整えなければ。そう強く感じたと石坂さんは言う。
「現場の職員が声を挙げて活動することもできますが、社会の仕組みをつくる側に立って、改善していくのもひとつの方法だと思ったんです。また同時に、僕とパートナーとで“東京メトロポリタンゲイフォーラム”というサイトを立ち上げて、選挙の際に候補者にアンケートをとって、同性愛者に対しての考えや政策を聞き出して掲載していたんです。でも、それだけでは社会は変わらないことも感じていて、やはり自分が議員になるしかないと」
マイノリティである中野区議会議員として
そして、石坂さんは2011年より中野区議会議員となった。性的マイノリティだけでなく、社会的にマイノリティとされるすべての人が生きやすい社会を目指して、様々な仕組みを築こうと奔走している。
「誰もが不安や孤立を感じずに生きられる社会にしたいと思っています。同性愛者だと自覚してから、不安や孤立を感じて生きてきたからこそ、強く思うんです。自分の周りにいる同性愛者、さらに広げてLGBT、障碍のある人、外国籍の人、シングルマザー……、みんながいろんな問題を抱えて生きていて、完全に一致した共通経験はなくとも、自分がマイノリティだからこそ気づくこと、共感できることはあると思います」
実際に、シングルマザーから「法制度で守られていない存在として、同じような経験をしていて共感できる」というコメントが寄せられたり、障碍者支援団体の関係者から「同じ社会的マイノリティとして、ぜひ応援したい」とエールが送られたという。
07性的マイノリティのメンタルヘルス
依存症や鬱に陥らないために
「今、力を入れていることのひとつに、性的マイノリティの心のケアがあります。僕自身はカムアウトして、運良く概ね周囲にも受け入れられたけれども、カムアウトできない、カムアウトしても受け入れられなかったなどの苦しみから、メンタルヘルスを崩してしまい、依存症を抱えてしまったり、働くのが難しいほどの鬱になってしまったりする人も少なくないんです。なかには、行き場をなくしてホームレス状態になっている人もいます。そうならないためにも、メンタルヘルスを初期段階からサポートできる仕組みをつくろうとしています」
サポートできる仕組みのひとつには、相談窓口を目に付きやすいかたちで設置するということがある。それと同時に、おそらくはセクシュアリティに気付き始める年代の、子どもがいる教育現場でも、相談できる場所をつくることは必要だ。
「教師、保健室の先生、学童や児童館の先生に基本的な知識を身につけていただいて、子どもたちが相談したときに、正しく対応できる環境をつくりたいと思っています。今年の4月に、文部科学省から性同一性障害の児童生徒に対する学校での対応例をまとめたものが、全国の教育委員会に通知されました。まさに今、学校が具体的な環境づくりを求められているところなんです」
変わっていく学校とLGBT
文科省が2013年度に実施した全国調査によると、自分の身体の性別に違和感を訴える小中高生は606人にのぼったという。そのうち、性同一性障害だと診断されたのは165人。この現状を考慮して、生徒が自認しているセクシュアリティに合わせて制服を選べるようにしたり、教職員が性同一性障害や性的マイノリティに対する否定的な言動を慎むように求めたりと、教育の現場も変わろうとしているのだ。
「もちろん、性的マイノリティの大人に対するサポートの拡充も必要です。ただ、性的マイノリティについては、問題がセクシュアルな部分に絡むことが多いことなので、相談に対して消極的なように思うんです。たとえば、HIVに感染してしまい、通院しなければならないので会社に伝えたいが、カムアウトできないため辞職してしまった人がいました。さらに、そのまま依存症を抱えてしまって、アルバイトもできない状態になり、生活するのも難しい状態に陥ってしまった人もいます。どうしても、もっと早い段階で相談してくれなかったのか。そう思うことが本当に多くあります。もっと多くの人が、相談できる機会が得られるように、誰の目にも見えるかたちで、誰に対してもオープンな相談窓口が必要です」
08同性カップルで暮らす難しさ
同性カップルに対する住民の苦情
石坂さんは現在、2001年から交際がスタートした男性と一緒に暮らしている。付き合いだしてすぐに、お互いのお母さんとともに4人で食事をするような良好な関係が築けたのだという。社会に向けてもカムアウトし、家族からの理解も得てもなお、同居を始めるにあたっては苦労もあった。
「僕たちが一緒に暮らす家を探したときも、同性ふたりで住める物件が限られていました。さらに男性同士となると断られることも多くて。間取りを見て、気に入った物件があったとしても、なかなかOKが出ないんです。同性カップルでも住める物件をやっと見つけて、住み始めてからも、管理組合から大家さんに『どうして同性カップルに部屋を貸したんだ』と苦情に近い問い合わせがあったりもしました。周りの同性カップルや友人同士でルームシェアしたい人からも、同じように家探しに苦労していると聞いたので、中野区の住み替え支援制度のサポート範囲を同性カップルや同性の友人同士の同居にまで拡張しました。今では、物件が見つかるよう、区が家探しをサポートしてくれます」
住まいを見つけること以外にも、同性カップルで暮らしていくことには不安や不便は尽きない。ある日、パートナーが入院したときにも、困難の可能性を感じたという。
パートナーの危機と困難の可能性
「彼が胆石に入院したんです。入院の同意書と胆石の手術に関する同意書は、本人の意識があるうちに彼が自筆でサインしました。でも、もし、手術の最中にがん化した部位が見つかったら。麻酔のかかった状態で本人の意思は確認できません。僕が親族であったら、手術を続行する同意書が書けたかもしれないのですが、それも難しく。そういった場合には、法律上では赤の他人である僕では同意することはできず、手術は一旦終了し、麻酔が回復した本人の意思を待つことになってしまうのです」
実際には、医療機関によって、誰の同意がどこまで有効であるかは差があるのだが、大切なパートナーの一大事に“自分は他人である”という事実を突きつけられることは耐え難く、できることであれば避けたい。
そういった様々な経験のなかで、石坂さんとパートナーは共同生活を営むにあたって、お互いの療養看護、財産管理などに関して、自分の権利を相手に委任するという意思表示を公正証書というかたちで示している。同性婚が認められない日本では、この公正証書の作成は、夫婦に近い関係を維持するためのひとつの方法といえるだろう。
09あと10年で夫夫の銀婚式を
制度が整ったら、式を挙げたい
15年近くも交際を続けている石坂さんとパートナー。「思えば、山あり谷ありでしたよ」と石坂さんは笑うが、その山も谷も一緒に乗り越えてきた、いわば戦友のような固い絆で結ばれた関係だ。彼との未来は、どのように考えているのだろう。
「今では、法律上は結婚が認められていないけれども、式を挙げる同性カップルが増えています。僕たちも周りから『式は挙げないの?』と聞かれることが多いです。パートナーは市民団体として同性パートナーシップ制度を推進する活動を行っているので、もしそれが、同性婚というかたちで実現できたら、利用したいと思っています。やはり、制度が整う前に式を挙げるよりも、満を持してというほうがいいかなと。あるいは、ふたりの生活が付き合った瞬間からスタートしたとすると、あと10年ほどで銀婚式のタイミングなので、そのときに式を挙げられたらいいよね、なんてパートナーと話したりもしてるんですよ」
DVの男性被害者の避難場所を
石坂さん自身も、先に述べた中野区の同性カップルを含む住み替え支援制度のサポートのほかにも、様々な同性カップルのための仕組みづくりを行っている。
「渋谷区では『渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例』が可決され、条例での同性パートナーの保障が始まります。中野区では、同性カップルの不都合を一気に解決するような仕組みでは、まだないですが、まずは、住宅のほかにDVの相談も窓口でできるようになりました。異性カップルと同様に、同性カップルでもパートナーの暴力からの救いを求めている方がいるんです。しかし、東京都が用意している被害者保護のシェルターは男性の避難を想定していないので、区のDV相談にせっかくつながっても、そこから先について保護をする体制がとれていなくて。以前ご相談を受けたなかで保護が必要だった方には、僕の個人的なつながりから、障害者施設に避難していただいたんですが、現状ではまだ、区で相談は受けられるけど、保護はできない状況なんです。それが今後の課題ですね」
ほかには、同性愛者が相談しやすいようにHIVの相談機会の整備も行っている。自らの性的指向が周囲に知られることを恐れて、なかなか相談ができないままでいる同性愛者が多いという現状を考慮したものだ。
「一歩一歩ではあるけれど、社会が変わってきている実感はあります。中野区では、この変化の延長線上にパートナーシップ制度などがあるのだと思っています」
10人が変われば、世間も変わるはず
少しずつ偏見をなくしていく
正月は毎年、自身の実家にパートナーと一緒に帰省し、家族団らんで過ごす石坂さん。パートナーの故郷である札幌で“レインボーマーチ札幌”が行われたときには、彼の実家にも訪れていたという。お母さんと一緒に、セクシュアルマイノリティの家族のサポートをテーマとした講習会に、ゲストスピーカーとして参加することもあった。
石坂さんとお母さん、そしてパートナーとその家族との信頼関係は、根気強く、何度もボールを投げ続け、打ち返し続けたからこそ築けたものだ。
「カムアウトしたときに母から言われたことが心に残っています。『自分のなかに偏見があったから、受け入れられなかった。世間に偏見がなかったら、私も悩まなかったかもしれない』と。また、ある人はご両親から『法律やシステムを変えたら社会は変わるかもしれない。あなたの言葉で親の気持ちは変わるかもしれない。でも、世間は簡単には変わらない』と言われたそうです。確かに、世間という実体のないものを変えるのは難しい。でも、世間は人でできている。人が一人ひとり変わっていけば、いつか世間が変わるんじゃないかと思うんです」
声を正しく届ける大切さ
そのためにも当事者がまず、周囲に届けようと声を上げることが第一のステップ。そして、その声を聞いた周りの人が受け入れることが次のステップ。さらに、その人々が周りの人に正しく声を届けていく、この繰り返しが大切なのだ。
「声を“正しく”届けることも重要です。誤った情報は性的マイノリティに対する偏見を生む可能性があります。特に、学校の教員や福祉施設の職員、子をもつ親であれば、同性愛嫌悪や同性愛蔑視の発言は間違っていると子どもに伝えてほしいんです」
趣味はマラソンや駅伝。まっすぐにマイノリティも住みやすい社会という明確なゴールを見据え、ひたむきに走り続ける姿は、まさにランナーだ。自分自身とパートナーの将来のため、中野区に住む社会的マイノリティのため、そしていつかは世間が変わり、日本全体に本当の意味での平等が広がる未来のため、石坂さんは今日も走る。

3.jpg)

1.jpg)
1.jpg)


