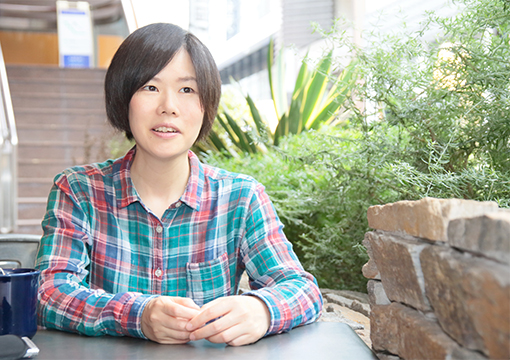02 自分は男なんだと自覚して
03 いや、腐男子なんだと自覚する
04 からかう周りを、見下していた
05 男と女の気持ち悪い分かれ方
==================(後編)========================
06 初めて好きになった男の人
07 高校でプチ不登校になる
08 その原因は、発達障害
09 結局、誰も悪くないんだよ
10 私、Xジェンダーなんだ
06初めて好きになった男の人

BL愛は深まる
中学生になって、BLの漫画本を初めて買った。
「マスクをつけて、近所の本屋さんにこっそり、買いに行きました」
「そのうち堂々と買いに行くようになりましたけど(笑)」
初めてBLゲームを買ったのは中2のときだった。
好きなキャラを攻略するのが楽しいし、サスペンスの要素や、一筋縄ではいかないダークで深い、複雑な世界観も好きだった。
「私、根っからのオタクだから、なんか物語がすごい好きで。物語やシチュエーションにドキドキするタイプ。そういうのを見つつ、BLも見つつ」
好きな世界を深めることは、楽しかった。
うれしいことに、この趣味の話をできる人が、学校で見つかった。
1年上の先輩で、男性だった。
「実はその方が、ゲイだったんです」
BL好きなら、きっとわかるだろう言葉を、ぽろっと言ってみたら、「お前、なんで知ってるの?」と、反応してくれた。
「そこから仲が良くなって『実は自分もゲイで・・・・・・』と、彼のほうから言ってくれたんです」
彼のことを、好きになっていた。
男性を好きになったのは、この人が初めてだ。
「でも、好きになってはもらえなかった。・・・・・・片思いですね」
新しい担任の先生
好きになった先輩には、自分のことは「腐男子」だと言っていた。
「自分のセクシュアリティが何か、すごく迷ってたんです」
「でも、同性愛である、ということは、否定したかった」
ゲイ? バイセクシュアル?
それとも、ただの腐男子?
自分のセクシュアリティへの認識は、いつも揺れ動いていた。
だが、そのことをまっすぐに受け止めてくれる人が、登場した。
中3のときの担任だ。
吹奏楽の強豪校の顧問を経て、自分の学校に来たその先生は、30代前半の女性だった。
「その頃、なんか、いじられることが少なくなったな、と思っていたら、その先生が、自分をからかっていた子に注意していてくれたんです」
それがわかったのは、三者面談のときだった。
母が思わず「この子、女の子っぽくて」と漏らした。
すると先生は「からかう子がいたから、私が注意しましたよ」と言ったのだ。
「先生は多分、私がマイノリティ側の人間だ、ということを見抜いていたんです」
「でも私は、それを自分からは、どうしても言えなくて・・・・・・」
本当は、どうなの?
親も、先生も、親身になってくれていた。
自分に真剣な眼差しを向けて、問うてくれていた。
「本当は、どうなの?」
でも、やっぱり、まだ、答えられなかった。
「女の子になりたいの? 男の子が好きなの?」
繰り返される、母のそんな問いには、「いや、違うよ」と答えてきた。
「たぶん母としては、ずっと昔から疑念があったから、受け入れる体制でいたと思うんですよ」
母は、性別違和と同性愛の混ざったようなもの、として自分をとらえていたのだろう。
だが、ずっと否定してしまった。
「正直、聞いてほしくなかった」
「なにかの拍子で、バレるのが怖かったから」
これが何なのか、自分でもよく、わからなかったのだ。
07高校でプチ不登校になる
ヘトヘトになる高校生活
地元の公立高校に進学した。特進クラスに入り、部活は演劇部にした。
部活では「オペラ」という風雅なあだ名で呼ばれる。
「ウチの演劇部は、入部当初にあだ名を付けるという通過儀礼があったんです」
「それで、自己紹介でオペラが好きと告げた結果、オペラというあだ名になりました」
特進クラスには、朝の講習や放課後の講習があり、勉強漬け。
それに、演劇部の活動も忙しかった。
「家に帰る頃にはくたくたになって、勉強もほとんどやれなくなってしまって・・・・・・実質、ヘトヘトになっていました」
これに追い討ちをかけるように、同じクラスの女子生徒の約半数から、突然、シカトされてしまう。
「今までも、小学校から中学校、中学校から高校とあがるたびに、今度こそうまくやりたい! と思うんだけど、毎回、失敗してしまって・・・・・・」
辛い出来事はしかし、これまでの自分のありかたやふるまい、言動を、振り返るきっかけとなった。
「これは、周りが悪いんじゃない。私が悪いんだって、そのとき初めて気づいたんです」
「それまで、すごく天狗になっていた自分が一気にガクンと崩れて、自分って、なんてダメな人間なんだって、思いました」
「本性が、かまってちゃんだから、やたらと人前でなんかやっちゃったり、喋りすぎて相手に嫌な思いをさせることが多かったんだと思う」
休み時間は、身の置き場がないと感じ、空き教室に逃げ込んでいた。
孤立していた。
学校には、行きたくなくかった。
でも1年のときの担任は声の大きな女性で、今でも夢に見るほど怖かったから、登校前にさめざめと泣き、諦めの気持ちで、学校に行った。
「学校に行かないと殺されるという強迫観念がありました」
地獄だった
そんな中、心の支えは演劇部、のはずだった。
先輩から、演出補佐としての役目を期待されていた。
しかし、それもしんどくなっていた。
一生懸命やったつもりでも、手順が悪かったり、さぼっていると思われた。
「演劇部でも先輩にめちゃめちゃ怒られて。確かに当時の私もいろいろ問題があったんだけど、部活にも強迫観念で行っていましたね」
自分なりに、人間関係において気をつけなくてはいけないことが、なんとなく見えてきてはいた。
「でも、もう手遅れの状態。今さら自分が改心して何かを変えたところで、周りはもう変わらない」
一度貼られたレッテルを、新しく上書きするのは、至難の技だった。
「地獄でしたね」
夏休みが終わり、学校に行けない
高2になると、学校に行くことが、さらにしんどくなってきた。
陰でコソコソ、裏でネチネチ。
そんな気配を、背後に敏感に感じていた。
「髙井は同性愛者じゃないか、オネエなんじゃないか、とクラス中に一気に広まったんです」
中学の時のような、無邪気なからかいとは、明らかに違った。
「濃い疑いとして、コソコソ言われちゃって」
やがて、体にも異変が出た。胃がキリキリと痛む。
ついに、学校に行けなくなってしまった。
最初は親の目を盗んで、ちょこちょこサボっていた。
高2の夏休みが終わり、学校が始まった。
しかし、もう学校には行けなくなっていた。
母親の声色を真似て、学校に電話をかけた。
そのあとは街なかをぶらぶらしたり、公立図書館にこもったりして、時間をやり過ごした。
08発達障害だった

姉のひとことがきっかけで気づく
学校に行けなくなる直前、高2の夏休みの真っ最中。
母と、帰省中の3歳上の姉と、自分とで、食事の準備をしていた。
「姉は自分とは正反対のタイプ。男勝りで、成績もよく、私も姉にはからかわれることが多かったけど、仲はいいんです」
そんな姉に、食事の準備の段取りで、同時に2つ、3つのことをやってと指示された。
その様子を見た母は「だめだよ、政吾は3つ以上のことは同時にできないんだから」と姉をたしなめた。
母の言葉を、自分への嫌味だと感じつつも、母の言葉を受けて姉が発した言葉が、鋭く耳に刺さった。
「政吾、あんた、何かあるんじゃないの? 病気みたいなものが」
姉にそう言われて初めて「自分は、何かあるんじゃないか」と思ったのだ。
「ADHDなどの存在は知っていましたが、メディアに出てくる人って、本当にたいへんな症状だったりする。だから、果たして私はADHDと言い切れるのか、ずっと葛藤があったんです」
さっそく、大きな書店や図書館で、発達障害に関連する書籍を手に取った。
夏休みあけの不登校の間にも、発達障害の本を読み漁った。
「本を読んでやっぱり、どうも私は、これっぽいなと思ったんです」
最初に信じてくれたのは、保健室の先生
夏休み明けの不登校は、1週間ほどで、親にバレてしまった。
同じタイミングで、「自分には発達障害があるかもしれない、疑い始めている」と母に訴えた。
「自分は発達障害なんだから、早く発達支援センターに連れて行ってよ」
感情が溢れ出し、大声で、泣きながら母に訴えた。
でも、不登校に怒っている母は、聞く耳を持ってくれなかった。
「『政吾が自分で勝手に決めついているだけ。逃げでしょう』と言われて」
高校にもまた、行かなくてはならない。
でも、教室にはもう入れない。
仕方なく、泣きながら保健室に行った。
これが、功を奏した。
「一番最初に、私が発達障害だということを信じてくれたのは、保健室の先生だったんですよ」
不登校中に買った、発達障害の本を、保健室の先生に見せた。
「先生、正直に言ってください。僕にこれ、あると思いますか?」
先生に問いかけた。否定されるのが、怖かった。
すると「あると思うよ」と言ってくれた。
「違うわよ、何言ってんのよ」とは言われなかったことに、救われた。
保健室の先生は、親身になって受け止めてくれ、スクールカウンセラーに相談することを勧めてくれた。
親や担任を説得してくれたスクールカウンセラー
スクールカウンセラーに、話を聞いてもらった。
「発達障害かもしれない、ってことを、今まで誰もわかってくれなかったのに、そのカウンセラーは、親身になってわかってくれたんです」
「実は、男性が好き」ということも、少し話すことができた。
そして、スクールカウンセラーは、母と担任の先生に、自分の抱える発達障害のことを説明してくれた。
今まで周りの大人は、自分が一生懸命に訴えてもわかってくれなかったけれど、スクールカウンセラーの言葉には、きちんと耳を傾けていた。
「代弁者がいるということは、とても心強いんだと思いました」
周囲の大人たちの理解を得ることができたのだ。
そして、地域の発達支援センターへ、母と一緒に行くことができた。
ADHDと自閉スペクトラムの傾向があることが、判明する。
09結局、誰も悪くないんだよ
自分を受け止め、許したい
学校に行けなくなった自分を、情けなく思い、恥じていた。
「親にも迷惑かけてるし、自分自身を否定するしかない環境で、弱い自分が本当に許せなくて」
だから、答えを見つけたかった。自ら発達障害を疑ったのも、そのためだ。
自分の生きづらさの原因がわかり、自分を許してあげることができたら、どんなに心が、楽になるだろうか。
発達障害であることを周囲が受け入れてくれ、自分もそれに向き合うことで、心の状態に、変化が訪れた。
「自分のことを許してあげられたことが、大きかったですね」
「もともとこういう傾向があるからこうなんだ、だからそこに向き合えば、もっとよくなっていけるんだってことが、具体的にわかってきたんです」
光が差してきたようだった。よし、もうちょっとがんばってみよう。
「そこから、アスペちゃんである自分との戦いが始まりました」
高2の秋が、深まろうとしていた。
さまざまな感情の行き場
みんなとは、違うものが好き。興味や視点が、みんなとは違う。
今まで、なぜ周りとうまくいかなかったのか、発達障害であることできれいに説明がついた。
「すごく辻褄が合うんです」
ただ、母は複雑な気持ちを抱えていた。自責の念に、苛まれていた。
・・・・・・お母さんが、悪かったのかな。
・・・・・・産み方が、育て方が、悪かったのかな。
それは違うよ、お母さん。違うんだよ。
「発達障害って、結局、誰も悪くないんです」
発達障害とは、ただただ、そういう傾向があるというほどのこと。
「ただ、誰も悪くないと、感情の行き場がなくなっちゃって、結局、頼んでもないのに自分を生んだ親が悪い、そもそも自分が生まれたことが悪い、と思い詰めてしまうんです」
まず、自分を許した。
そして、クラスメートに白い目で見られても、学校には通った。
演劇部の仲間にカミングアウト
再出発した高校生活。折しも、演劇部は合宿シーズンだった。
宿泊していた男子部屋に女子部員が集まり、5人程度で和気藹々と雑談が始まった。
「オペラ、最近学校来てなかったけど、どうしたの?」と仲間の一人が聞いてくれた。自分のことを心配してくれていたのだ。
親と戦い、担任と戦い、発達障害と向き合い、と夏の終わりの激動の日々を聞いてもらった。
そしてもうひとつ、今まで隠してきたことを、話してみた。
心配してくれた仲間だから、話してもいいかな。
そんな気持ちだった。
「実は僕、男の人が好きなんだ、って」
性的指向は、バイセクシュアルだとも明かした。
これが初めてのカミングアウトだ。
ドン引きされないか怖かったが、勇気を出した。
どうせ嫌われるのなら、今のうちに嫌われてしまえばいいんだ。
そんな諦め半分、期待半分の状態だった。
演劇部の仲間は、わかってくれた。受け入れてくれた。
「オペラ、それを思いきって言えるってことが、すごいよ」
うれしい言葉だった。否定なんか、全然されなかった。認めてくれた。
わかってくれる人がいるんだ。それを実感することができた。
ここにいても、いいんだ。
部活が、自分の居場所になった。
10私、Xジェンダーなんだ

人を助けられる人になりたい
高校卒業を目前に、将来、本気で進みたい道ができていた。
大学で福祉を学び、社会福祉士を目指すという目標だ。
「スクールカウンセラーに出会ったことで、私も人を助けられる人間になりたい、って思うようになったんです」
スクールカウンセラーは、生きづらさを抱えた自分のことを否定せずに、今までいろいろなつまづきがあったことを、しっかりと受容してくれた。
それだけでなく、自分では気づかない強みを見つけて、教えてもくれた。
そして、弱い立場の自分の気持ちを、代弁してくれた。
「戦うんじゃなくて、誰も傷つけることなく、みんなが受け入れるようにしていくんです」
今、大学で社会福祉を専門的に学んでいる。
制度には “はざま” がたくさんあることを、実感するようになった。
学校教育のあり方にも、疑問を感じている。
「子どもの世界、学校って、つくづく残酷なんだなって思います。学力で人をはかり、集団生活で人を型にはめる」
自分にとっても学校とは、個性が尊重される場所では、決してなかった。
「学校という型は合わなくても、社会で活躍する子はいっぱいいるじゃないですか」
私、Xジェンダーなんだ
大学では、最初からカミングアウトした。
「えー、そうなんだ、って感じで受け入れられました」
セクシュアルマイノリティのサークル・早稲田のGLOWにも入り、そこで「Xジェンダー」という概念を、初めて知る。
「その言葉を初めて聞いて、ビビっと来て、私、これなんだって」
それまで、自分の中の女性的な部分、中性的な部分について、なんだろう、と思っていた。当てはめる言葉が、見当たらなかった。
だが、男と女を飛び越えた概念を知り、しっくりと来る感覚を覚えた。
ゲイ? バイセクシュアル? 腐男子?
いや、Xジェンダーなんだ。
「性的指向は、いろいろな人に惹かれるところがあって」
「でもパンセクみたいにすべてのセクシュアリティに惹かれるわけではないから、ポリセクシュアルかなって自認しているけど」
「結果的に、よくわかんない(笑)」
姉と母へのカミングアウト
大学に入学して最初の夏に、姉、母の順でカミングアウトした。
「そうなんだ、前からそうだと思ってたよ」
姉はさっくり、受け止めてくれた。
母には、電話で口喧嘩がエスカレートした最中に、告げることになった。
「そんな気はしてた。政吾、私は、あんたの発達障害を受け入れることのほうが、大変だったよ」
後日、なんで受け入れてくれたのか、もう一度母に聞いてみた。
「だって、政吾がXジェンダーというのは事実なんだから。事実は変えようがないから、親としては否定する選択肢はない」
母の言葉が、嬉しかった。
誰も悪くないんだ、というところに、たどり着いていた。
父へのカミングアウト
父にカミングアウトしたのはその1年後、去年の夏だった。
消防士として、体育会系の男社会を生き抜いていた父。
子どもの頃からずっと、おそれ多い存在だった。
「父の性格は温厚で、良く考えたら別に怖い人ではないのに、なぜか私にとっては、ただただ怖いイメージで。それまで、じっくり話すこともなかったんです」
夏休み、実家に帰省して再び東京に戻る日。
手紙を書いて、父の部屋の机の上に置き、家を後にした。
ほどなく父から、メールが届いた。
「政吾には政吾の良さがある。政吾は政吾で、お父さんと違って当たり前なんだよ」
うれしくて、胸が、詰まった。
振り返ってみると、父は私を否定したことなど、一度もなかった。
高校の不登校のときは少し怒られたけど、発達支援センターに行くことだって、父はすぐに認めてくれた。
「父のおかげで、私は自由でいられたんだし、父が私の個性を受け入れてくれたから、今の自分があるんだと思います」
社会福祉の勉強に燃えている。
「熱意だけでは、人は救えないんですね」
「ちゃんとした手順に沿って人を支援していかないと、場合によってはクライアントを傷つけてしまいかねないんです」
「だから、セクマイの中でもソーシャルワーク理論を根付かせたいんです」
人々の暮らしに生起する、困難な問題を解決していきたい。
セクシュアルマイノリティも、セクシュアリティだけによって困難に見舞われるのではない。
実際の生活では、それぞれのセクシュアリティに対応して、それぞれの局面で、それぞれ個別の、解決すべき諸問題が、次々と生起してくるのだ。
「いろんな人からエッセンスを学んで、自分なりのソーシャルワークを展開していきたいと思っています」
今、人を支えるプロフェッショナルを目指している。