02 オランダで出会った、恋
03 パフォーマーとしての日々
04 初めての恋人と、家族へのカムアウト
05 彼女との別れと、支えてくれた人
==================(後編)========================
06 パフォーマンスアーティストとして、本来の自分を表現したい
07 カムアウトはしたい人がすればいい
08 これからのセクシュアリティ問題について
09 母という人
10 パフォーマンスは続ける!!
06パフォーマンスアーティストとして、本来の自分を表現したい
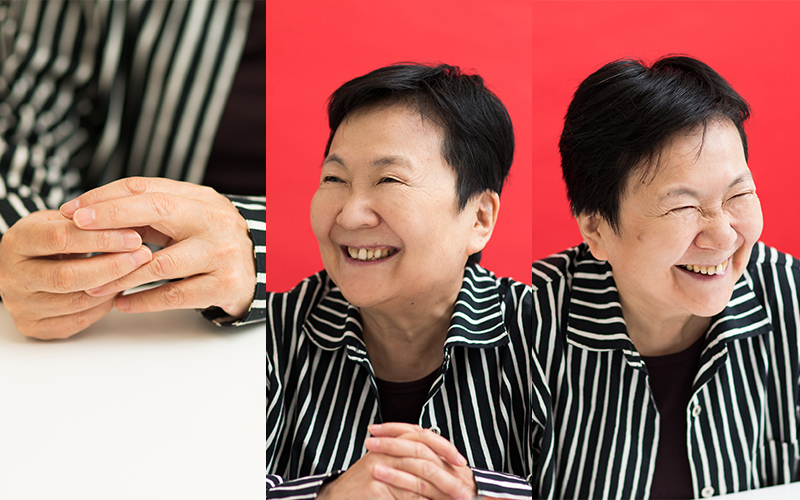
自分を隠すことのつらさ
「若い頃は、飲み会って大嫌いでした。ぜったいに恋の話になるでしょ。付き合ってないのに、男友達がいるみたいなフリをしたり、嘘をついたりしなければならないのが、もうたまらなくて。付き合い悪いなって言われながら、誘いは断っていました」
オランダやカナダで、女性が自分の生き方を自分自身で決めていく様をさんざん見てきた。それが向こうでは普通だった。
「日本でもそうあってほしいと思っていました」
初めて自分のセクシュアリティに気づいた20代。初めて女性に告白をした30代。
そして初めての恋人との出会いと別れ、家族へのカムアウトをして、今の自分がある。こうした経験をふまえて、本来の「自分」を表現したいという気持ちが、どんどんふくらんできたという。
自己肯定感からうまれた『自画像』
「恋愛はダメになってしまったけれど、これまでの経験で、自分がレズビアンだということがはっきりしたし、この頃から、私の中ではすごく自分が解放されたというか、ようやく自分を肯定することがでるようになってきたんです。それが、とても嬉しかった」
そうした自分の心の動きと向き合うようにして生まれた作品が『自画像』だった。
レズビアンであることは、自分の一番大切な、根幹をなすもの。それを封印して今後も創作活動を続けていくことはできない。そんな決意から生まれた作品だ。
パフォーマンス・アートは、誰かの作った台本や振り付けがあるわけではない。本人が、そのありのままで行為していくアートなので、肝心のセクシュアリティのところだけぼかしているのは、アーティストとして良くないと思っていたと言う。
「表現者として、いろんな考え方があるでしょうけど、そのときの私はそう思った。そして、やらなければならない、という義務感からではなく、心からやりたいと思って実行したんです」
07カムアウトはしたい人がすればいい
私のカムアウトに反応してくれる人がいた
ターリさんの代表作の1つ『自画像』は、1996年初演。その後2年にわたって25回余りのパフォーマンスを行なった。
「東京だけでなく、大阪や京都でもパフォーマンスしました。なかには『レズビアン』という言葉を使うな、と言ってくる施設もあったりして。それが当事者にとってどんな意味をもっているのか、無自覚な発言というか検閲ですよね。その時は『私は女を愛する女です』と表現を変えたの(笑)。セクシュルマイノリティが存在していることを知ってほしいと思ったし、そのためにもパフォーマンスがあるということを知ることができました」
観客の中には、終演後楽屋を訪ねてきて、「私も実はレズビアンです」と言いに来る人もいた。
そんな反応を受けて、日本でももっと、カムアウトが広がったらいいのにと思っていた。
「でも今は、カミングアウトに関しては、慌ててしなくていいと思っています。移ろいやすいじゃないですか、セクシュアリティって。決めつけることもないし。ある種の覚悟と必然性といったものがあれば、してもいいと思うんですけど。ただ、やっぱり問題は自分たちよりも、マジョリティのほうにあるんだってことは、ちゃんと知って欲しいですね。自分たちが単に少数(マイノリティ)ということで、負なる存在だって思わないで欲しい。それで悩んじゃって、自殺しようとする人もいっぱいいるでしょ」
パフスペースで安心できる出会いを
2003年、精力的にパフォーマンスやワークショップを続ける中、「パフスペース」という多様な人々が交流できる場を開いた。
表現を通して人が繋がれる空間作りをめざし、「ターリスタイル体操」を教え始めたのもここで。はじめはレズビアンの人たちが集まってきた空間だったが、しだいにLGBTや様々な人がなごやかに集える、コミュニティスペースとして機能するようになっていった。
「自分のことを言いたくて仕方がないときってあると思うんです。そんな時、この人には言えそうだなと思える人と出会えることは大切なこと。今は隔月に一回、中目黒の一室を借りて、フリートークというか、気軽におしゃべりができる場『パフカフェ』を仲間と主催しています。30代から40代の人が中心で、とても落ち着いた雰囲気ですよ。コミュニティーといっても向き不向きがあるので、色んなところに行って自分に合うところを探してみて欲しいです」
08これからのセクシュアリティ問題について

何が変わればいいのか
まだ「LGBT」という言葉がまったく知られていない頃から、フェミニズムやセクシュアリティ問題について、深く関わってきたターリさん。現在の社会の動きを見ていると、いい意味で変わってきたものと、なかなか変わらないものがあることを痛感している。とくに最近気になるのが、日本の若い人たちの “カップル志向” が強いことだ。
「同性婚というけれど、そもそも結婚制度っていったい何なのかと。カップル単位が基準のあり方だと、普通と思われているでしょ。でも、2人になる人もいるし、1人で生きていく人だっているし、もしかしたら3人で暮らす人たちだっていたりするかもしれない。そういうのが許されて同じように保障される、より自由な社会になればいいなと思っています」
欧米での生活で知り合った友人たちの「個」を大切にする個人主義は、とても自由で魅力的に映った。対して、日本の「家制度」ともいえる家族単位の考え方にどうしても馴染めない。
同性婚にそんなにこだわらなくても、個人が幸せに暮らせる制度の充実を図るほうが、先だし大事に思えるのだと穏やかに話す。
自由を自分でつかみとってほしい
「セクシュアリティって、いくつもあるアイデンティティのなかのひとつでしかないんです。恋人と良い関係を築くためには、セクシュアルマイノリティであっても、生活の仕方や物事への価値観を共有していくことが大切ということに気づきます。関係のバランスの取り方は千差万別、外から言うのはつまらないことだけれど、だけど、私は『自分』=『個』を基本とするのが良いと思います。誰かに依存してしまうと自分を失ってしまうから。自由を大切にして、他人との関係を作る。『自由』は自ら作って感じていくもの。この社会、そもそも自由じゃないもん。だから、意識的に自由を自分で掴みとって欲しい。あまり受け身になって欲しくないですね。セクシュアリティではマイノリティだけれど、他の側面ではマジョリティなんです」
だからこそ、支えてくれる人、理解してくれる人の存在はとても大事。
ターリさんの場合は、お母さんの存在がとても大きな、掛け替えのないものだった。
09母という人
どんなときも温かく支えてくれた人
「母が20歳の時に戦争が終わり、直後に母親と弟を病気で失いました。戦時下に果敢な10代の時を生きた母は、好きなことをやりたくてもやれない、許されない状況を受け入れるしかなかったのでしょう。結婚すると姑のわがままに振り回され苦労しました。振り回されたのは母だけでなく家族皆でしたが。娘にはやりたいことをやらせたいという思いがあったと思います。私に結婚しろとは言いませんでした。90歳になった今でも、毎日服や袋ものを作っている姿から、自己実現の意思を持ち続けたいという意思が強い人なのだと感じられるのです」
就職せずにアーティストになると言った時、レズビアンであることを告白した時、どんな時も、否定せず、お母さんは全力で応援してくれた。
作品づくりに協力してもらったことも
「尾辻さんが参議院選挙に立候補したとき、母に、事務所に手伝いに行くけど一緒に行く?って聞いたら、『行く!』と勢い良く返事してくれて。それで、一緒に手伝いにいったことがあるんですよ」
尾辻かな子さんは、日本で初めて同性愛者であることを公表して議員になった人。当時、新宿・アルタ前で行われた応援演説では、母子でマイクを握った。
「母はそれまで、社会的な活動に関わったことはありませんでした。ただ、私を通して、彼女なりに性的マイノリティに対する社会の扱いを体験してきたわけでしょ。それで、思うことがあって、一緒に手伝おうとしてくれたんだと思います」
それ以前のこと―― 1998年の作品「わたしを生きること」では、舞台上に映像としてお母さんの姿を投影した。
「写真家の誘導にのって(笑)、母も上半身ヌードを撮ってしまったんです。もともと、わりと自分を表現することを好む人ですから、躊躇はしませんでした。抽象画を描いたり、盲人用の絵本を作ったりしていましたし。あの人はすごい人、不思議な人です。それに、人が好きで会話を楽しみたい人だから、とっても人から好かれる人です。わたしの友人たちは開口一番『お母さんは元気?』と聞くぐらい」
誰よりも近くにいて、強く支えてくれた人。言葉の端々に、お母さんへの尊敬と感謝をにじませる。
10パフォーマンスは続ける!!

不自由になった脚
今、ターリさんは長距離を移動するときは車いすを利用している。
昨年検査入院をした結果、告げられた病状は、難病として知られる脊髄性筋萎縮症だった――。
「ここ10年くらいは、性的マイノリティからは少し離れたテーマでパフォーマンスを発表していたんです。日本軍の『慰安婦』のことや沖縄の基地のこと、福島の原発のことなどを取り上げて、表現活動をしてきました。そのために勉強しないといけないことがたくさんあったんです。生活費を稼ぎ、パフォーマンスをして、パフォーマンスのための勉強をして、現地を訪ね歩いて・・・。今は、あの頃はかなり無理をしていたな、ということがわかるんです。それで身体が悲鳴を上げてしまったんだなと。無理が徐々にあらわれたという感じですね。そんな実感がある」
病のため、ターリ体操教室やグループホームの夜間支援と介助の仕事から離れざるを得なかった。そしてなにより、もう以前のようには表現活動を続けていけないかもしれない――。
そんな不安に押し潰されることはなかったのだろうか。
病との闘い、そして生活の変化について、淡々と続ける。
「去年は大騒ぎして入院もしましたし、検査もしました。今年に入ってからはだいぶ落ち着いて、わりと自由に動けるようになってきたんですよ。力がないから、階段とかが大変ですけどね」
笑顔を見せ、しゃんと伸びる背中に、様々な壁を乗り越えてきた、その強さを垣間見せる。
表現したいことはさまざま
今はNPOの就業移行支援による研修を受け、イラストレーターやフォトショップを使ったデザインの勉強をはじめている。
「これも表現の世界だから、イヤじゃないです。というか本当に楽しいですね。それでなんとか、手に職をつけたい!」
ターリさんの作品にこめられているのは、「隠されていたことを可視化」すること。そういった思いが、それぞれの作品の根底に共通して流れている。
「フェミニズムを語るときによく言われる言葉として、“個人的なことは政治的なこと” というのがあります。女性の身体に起きることは、女性だけの問題だけではなく、政治や社会全体に問題があるということを指しているんですね。実は、この言葉が私のバックボーン。この言葉を意識してずっと物を作り続けています」
これまでと同じようなパフォーマンスは、できないかもしれないけれど「表現することをやめることはない」と、その瞳は真っ直ぐ前を向いている。
「表現することは、『社会とどう関わるか』につながる人生そのもの」
海を超えて果たした経験も日本で積み上げている活動も、決して「時の運」だけで得たものではない。時代を超えて掴みとり、確かに拓いている道。
これからの暮らしや夢について、穏やかな語り口で綴られた「ずっと創り続けていきます」という言葉。扉の向こうには、ターリさんが創るまた新しい未来がある。





