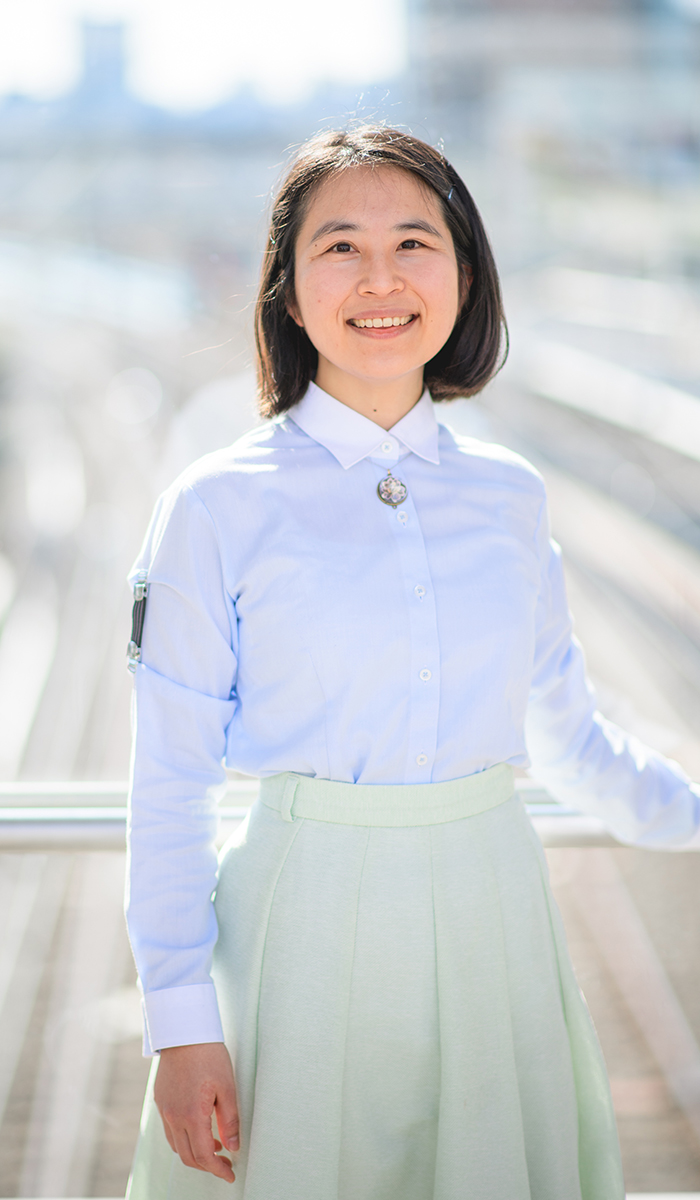02 情緒的なやりとりが薄い生育環境
03 小学校では毎年親を呼び出されていた
04 いじめが始まり、どこにも居場所がない時代
05 「毒舌」な自分の在り方は正しいのか
==================(後編)========================
06 恋とは違う「執着」の気持ち
07 「Xジェンダー」に衝撃を受けるも・・・・・・
08 しっくりきた言葉は「アジェンダー」
09 毒親との分籍
10 「大切な唯一の家族」と、自分らしく生きること
01言葉が早く、口が達者だった幼少期
引っ越しの多かった幼少期
出生は一応のところ北海道だが、住んでいた記憶はない。
「里帰り出産らしいんですけど、母子手帳が東京の所沢市なんで、たぶん私が1歳になるまでの間に引っ越したんだと思います」
最初の記憶は、1歳のときの電車の踏切の光景だ。
「2歳前後で石川県金沢市に移動したんですけど、そこの生活圏内には踏切がなかったんです」
「だから明らかに、その記憶は1歳の東京に住んでいたときの記憶なんですよ」
物心が付いたのは2歳のときだったため、東京から金沢に引っ越したときのことは覚えていない。
「私の中で引っ越しをしたっていう記憶がちゃんとあるのは、そのあと小学2年生で金沢から長崎に移動したときなんです」
環境の変化が多い幼少期だった。
父親を口喧嘩で負かす
言葉を覚えるのはとても早く、2歳にしてすでに父親を口喧嘩で負かすほどだった。
「母親が英文科の出身なので、とりあえず喋り出したら英語を習わせようと考えていたみたいで、2歳から英会話教室に通い始めました」
母親は教育熱心なタイプで、同時期に幼児教室にも通っていた。
「でも父親は、私が3歳のときに育児には関わらない宣言をしているんです(苦笑)」
父親のその宣言は、母親から聞かされた話だ。
前日にその件で両親が揉めているのを聞いていたため、特段驚きはしなかった。
「ああ、なんかそんなこと言ってたなあ〜っ、て感じで終わりました(苦笑)」
未成熟な両親の記憶
当時、夜中に両親がよく些細なことで喧嘩をしていた。
「一番くっだらないと思った喧嘩があって、食卓のお塩の容器の蓋がちゃんと閉まっていなくて、倒れて溢れたのがきっかけだったんですけど、・・・・・・」
「そこから1週間、両親が口聞かなかったんですよ(苦笑)」
傍観するわけにもいかず、「蓋を閉め忘れちゃったのはもしかしたら私かもしれないから、ごめんなさい」と言って仲を取り持とうともした。
喧嘩の原因が子どもである自分だったこともあった。
「そのうちに、我を忘れた両親のどっちかが私を殺しにくるんじゃないかって思って、震えてたこともありましたね」
喧嘩をした翌日、親はその事実や内容を自分が知っている前提で振る舞ってくる。
そのため眠らずにきちんと聞いていなければならず、翌日は怒らせないためにも大人しく静かに振る舞う必要があった。
「私にとってあの二人は、妹と弟みたいな感じなんです。私が面倒見てないとって、どこかで思っていましたね」
当時、自分の目に映る両親は、幼く未熟だと思っていた。
02情緒的なやりとりが薄い生育環境
理屈がすべての母親
無邪気に過ごしにくい家庭環境の中で、権力を握っていたのは明らかに母親だった。
「とりあえず母親にはある程度従っておかないと自分の命はない、みたいな感覚は、家を出るまでずっとありました」
声を荒げて叱りつけられることはそれほどなかったものの、母親は理屈がすべてで、感情の全てを切り捨てるような人だった。
「自分にやりたいことがあるときに、『◯◯っていう理由で必要なんです』ってことを説明しなきゃいけなくて・・・・・・」
「私がやりたいからやる、私がこれをすると嬉しいからやる、みたいな、そういう感情的な理由は認めない人でした」
感情を受け止めてもらえなかった
嬉しい・楽しいなどといった感情を、母親は共有してくれなかった。
気持ちを表に出すことは少なく、「とにかく、よくしゃべる子」だった自分の話を聞いてくれることもあまりない。
「いつも母親は『今忙しいの、私、暇じゃないの』『やることいっぱいあるの』って・・・・・・」
「いつ聞いてくれるのかなあ〜って待っていたら夜になって、そしたら『早く寝なさい』って言われるんです」
しゃべる量自体はとても多かったが、母親とのコミュニケーションはいつも一方通行だった。
ほめられるのは結果だけ
生活態度に関しても、母親は厳しかった。
「母親は規律正しい生活が好きだったので、片付けなさいとか、時間通りに動きなさいとか、そういうことでよく怒られてました」
成績に関してはよくほめられてはいたものの、評価されるのは結果のみだった。
「ただそれも、すごく喜んでくれるっていう感じではなくて、部分的にほめてくれるだけでしたね」
「『頑張ってるね』とか、過程を認められることはありませんでした」
「だから大学院生くらいのときに、生まれて初めて友だちに『頑張ってるね!』って、言ってもらったことがあって、その時は泣きました(笑)」
03小学校では毎年親を呼び出されていた
周囲に溶け込めず、男女で分かれる意味も理解できない
幼稚園では、なぜか周囲にうまく溶け込めなかった。
「みんなの輪への入り方がわからない。自分から他人に関わることができない子だったんですよ」
「なので、入りたい遊びをしてる子のそばにじっと立って見て、向こうから関わってくれるのをひたすら待ってるっていう感じでした」
そのころから、漠然と性別違和を自覚するようになる。
「だんだんと男の子と女の子が別々に固まるようになってきて」
「女の子がおままごとしてるところの近くに立ってると、構ってもらえるんですけど、男の子たちの近くに立ってても、絶対に構ってもらえなくなってきたんです」
一度「お前は男の子じゃないから入れてあげない」と言われたことを、なんとなく覚えている。
しかし自分には、その言葉の意味さえわからなかった。
「男の子じゃないことになんの意味が? って(苦笑)」
小学校に上がると、混乱はますます深まった。
「誰々ちゃんのことが好きって話題になったり、そのあたりから他の人がなにを言ってるか理解できなくて・・・・・・」
「“好き” って気持ちは私にもあるはずなんだろうけど、私が今特定の人に対して持ってる気持ちもそれと同じ? これは恋なの? ってずっと考えてました(笑)」
のちに自覚した性的指向は、「パンデミロマンティック・一言で説明できないセクシュアルですね」。
「自分に性別がないとわかったときに、他人に対しても性別を気にしていないってことに気がついて」
「だから理論的に考えて自分はパンロマンティックなんですけど、一目惚れとかはしないから、デミロマンティックっていう感じです」
毒舌な子どもゆえに
小学生に上がったころから、学校で「毒舌」と称され避けられるようになってしまう。
「他人の気持ちに配慮した言葉を語るということを、家で一切習っていないので、口を開けば正論しか出てこない子でした」
それは先生に対しても同じで、しょっちゅう自分にとっての「正論」をぶつけては喧嘩になり、毎年のように親を呼び出されていた。
「でも、親の方が正論こそ正義だと思っているから、かえって『お前はよくやった』みたいな感じで終わっちゃったんです(苦笑)」
初めて親の呼び出しを食らったのは、小学1年生のとき。
一階にあった教室には屋外に面した出入り口が一つしかなく、休み時間は混雑した。
出入り口の横には窓があり、そのすぐ下に暖房が設置されていた。
つまりその上に登れば、混んでいる出入り口を通らずとも窓から外に出ることができる。
「休み時間に、暖房の上に登って窓から出ようとしたところを先生に見つかって、『ちょっとあなたこっちに来なさい』って言われてたんですけど・・・・・・」
先生に「用事のある人が来てください」と、思わず言い返してしまった。
この言葉は、よく親に言われていたものだったから。
「『あなたの家は窓から外に出るんですか』って聞かれて、『うちは2階なので出られません』って答えました(苦笑)」
「私の中では論理構造は整っていて、出入り口が使えないなら窓から出ればいいじゃないっていう思考様式はいまだに変わってないんです」
04いじめが始まり、どこにも居場所がない時代
クラスメイトとの関係性が悪化
「毒舌」のせいで、クラスメイトにも避けられている気がするが、どうやって関係を築いていったらいいのかもわからなかった。
「小学5年生のときに、いじめられるようになってしまったんです」
首謀者は『親友だね』と言い合っていたほどに仲良くしていた子で、暴力こそなかったものの、無視や仲間はずれが始まった。
「体育でグループ作るときに余っちゃって、先生がその子たちに一応『入れてあげなさ〜い』って声をかけるんですけど、『いやで〜す』って返されてしまったりとか(苦笑)」
「先生もグルだったんで、別にそれを咎めたりとかもしないんです」
5年生の終わりに首謀者の子が転校したことで、目立ったいじめは落ち着いた。
「でもクラス替えもなかったので、6年生のときも浮いてはいました」
そのころ、習っていたバレエの教室でもいじめられていた。
「ほんとにあの頃、どこにも居場所がなかったです」
気持ちを落ち着けるために走った「自傷行為」
家庭でも学校でも習い事でも、常に息苦しい。
どうにか気持ちを落ち着けようとたどり着いた手段が、「自傷行為」だった。
「自傷行為をすると、安心したし、落ち着きました」
「感情に名前をつけることが上手にできなかった、というのも理由だと思います」
しかし、周囲の大人はSOSに気付いても手を差し伸べてはくれない。
「母親は見たくないものは見ない人なので、突っ込んで聞いてこない」
「わりと1年中、高校卒業するまで腕中傷だらけで、でも体育とか半袖で出席してたんですけど・・・・・・」
心のどこかで気付いてほしい気持ちがあったからこそ、見えるところに傷をつけていた。
「やめようやめようとは思っていて、高校生くらいのときに一度回数が減ったんですけど、断続的には続いていたんです」
「でも大学院のときに深くやってしまって、そこで初めて病院にかかったんですけど、そのときに『人に迷惑をかけるのはダメだからやめよう』って思って、刃物を使うのはやめました」
05 「毒舌」な自分の在り方は正しいのか
「荒療治」のため、あえて女子校に進学
いじめの加害者が女の子だったために、女性恐怖に陥る。
それを克服するための「荒療治」の意味もあり、中高一貫の女子校に進学した。
「志望校は特に偏差値高いところじゃなかったのに、なぜかバレエも辞めさせられて、難関校を目指すような個別指導の教室に通うことになりました」
「母親自身も女子校出身だったから進学先には賛成だけど、いい学校に進学してほしいって気持ちもたぶんあったんだと思います」
父親は俗にいう高学歴で、なおかつそれを鼻にかける人だ。
それを母親は嫌がっていたが、その一方で「子供をいい学校に行かせたい」という矛盾を抱えていた。
「母親の中の葛藤をそのままぶつけられてたのかな? って今は思いますね」
部活は禁止、習い事も・・・
母親によって部活動は禁止されていたが、自分自身さして部活を重要なものとは捉えていなかったため、強く抗議することもなかった。
「習い事もあって忙しかったし、別にいっか〜って思って」
「音大受験を期待されていて、ピアノ、英語、ソルフェージュ、
それと声楽を習っていたんです」
ピアノの才能はあったが、興味は持てず面白いとは思えなかった。
しかし、辞めさせてはもらえなかった。
「一度始めたことを辞めるのはすごくダメなことだっていう意識を植え付けられていて、『辞めたいなら辞めちゃいなさい』って言われるんですけど・・・・・・」
そこで「辞めます」と言うことは、絶対にできなかった。
「母親が見捨てた人に対してどういう扱いをするのか、父親を見ていてわかっているので、そうなるのが怖かったんです」
見捨てられたくなかったからこそ、気の進まぬ習い事も辞めることができなかった。
先生との喧嘩中、親友が過呼吸に
中学に上がっても「毒舌」のままだったが、だんだんと身の振り方を省みるようになった。
「中学2年生のときに、ある先生と大喧嘩になったんです」
「自分の理屈を通すことが主目的じゃなくて、単にその先生が気に食わないからいちゃもんつけるっていう・・・・・・」
先生とやり合っている様子を見た親友が、そのとき過呼吸を起こしてしまった。
また、その先生もその後しばらくして学校を辞めてしまう。
「たぶん私のせいもあったのかもしれない・・・・・。先生が学校を辞める背中を押しちゃった気がするんです」
「論理で相手を攻めるのって正しいんだろうか、みたいな思いを持ち始めた」
「社会に馴染もうとしたのではなく、他者の “個” としての主張を傷つけるのは正しいのか、ということについて考え始めました」
でも、改善すべきポイントに気付いても、当時はどうしたらいいのかはまるでわからなかった。
<<<後編 2022/09/03/Sat>>>
INDEX
06 恋とは違う「執着」の気持ち
07 「Xジェンダー」に衝撃を受けるも・・・・・・
08 しっくりきた言葉は「アジェンダー」
09 毒親との分籍
10 「大切な唯一の家族」と、自分らしく生きること