02 父が死んでよかった
03 母がいたから、いまの自分がある
04 話す代わりに書いて伝える
05 うつ病と上手く付き合いながら
==================(後編)========================
06 性同一性障害は体の障害
07 欠けた部分を取り戻す
08 運命の人には一生会わない
09 地元の性的マイノリティのために
10 困ったら、食べて寝ること
01女だったという記憶は、ない
性別違和は2歳から
思い出せる最初の記憶は2歳のとき。3歳の誕生日の前日のことだった。
「明日から3歳だね」と家族に言われたことを覚えている。
すでに「女の子らしくしなきゃね」などとも言われていて、それは違うと感じていた。
しかし、この頃は「自分は女ではなく、男である」とはっきりと意識していたわけではない。
ただ、「女ではない」という違和感は強く感じていた。
「近所にひとつ年長の男の子がいたんですが、女の子たちと遊ぶよりも、その子と遊ぶほうがしっくりきました。むしろ、私のほうが戦隊ごっこをやりたがったりとか、その子よりも男の子っぽいところがありました」
「その頃から自分が女だったという記憶はありません。どっちなんだろう、と悩んだ時期もないんです」
自分は女ではない。そこに揺らぎはなかった。
小学校入学の記念写真を撮るときに用意された服が嫌で泣いた。
紺色のブレザーとプリーツスカート、赤い靴、赤いランドセル。女の子っぽい格好は好きではなかった。
「私があまりに大泣きするので、親は随分苦労したみたいです。今だったらスカートでもなんでも喜んで着ちゃうんですけどね(笑)」
「でも、そのときの写真はもうないんです。そのときだけじゃなく、性別移行前の写真は全部。当時は過去を捨てる覚悟がないと性別移行なんてできないという時代だったので」
「惜しいことをしたなって思います。講演に呼んでいただいたときに、セーラー服を着ていた写真をお見せすることもできないし(笑)」
h3>縁を切ってくれてもいいから
過去は捨てた。
小学校と中学校の友達とは連絡がとれなくなっている。
しかし、月に一度は揃って食事に行くという高校時代の友達がいる。彼女たちには、ホルモン治療を始めた27歳の頃、手紙でカミングアウトした。
「当時は今よりも、性同一性障害は得体が知れないものでした」
「性同一性障害の人と付き合いがあるっていうだけで社会的な不利益を被るかもしれないという時代でした。だから、手紙には『私と付き合うことで嫌なことが起こる可能性があるから、縁を切ってくれてもいい』と書きました」
友達からは、いい返事も悪い返事もこなかった。
カミングアウトなどなかったかのように付き合いは続き、どの友達も男性として扱ってくれている。
「こちらとしては、スルーしないで何か言ってよって感じなんですけどね(笑)。それでいいの、ってこっちが心配しちゃうくらいです」
返事もせず、何も言わず、変わらぬ付き合いを続けること。
それはきっと友達からの最大の受容のかたちだったのだろう。
02父が死んでよかった
お腹を蹴られて
「話すのはあまり得意じゃないので、友達へのカミングアウトも手紙にしたんですが、実は中学生までは教師かコメディアンになりたかったんです」
「どちらも自分にとってはエンターテイナーです。多くの人に自分の知識や芸を伝えることで喜んでもらう仕事に就きたいと思っていました」
「親も、容貌がよくないのでコメディエンヌになったらちょうどいい、と言っていたので私もその気になっていて(笑)」
「でも、家族の前で何かを披露したことはありませんでした。家族と一緒にくつろぐということが、できなかったんです。父が暴力を振るう人だったので、父とはできるだけ違う部屋で過ごすようにしていました」
「自分の気に入らないことがあると暴れて・・・・・・。当時、私は父にとっては女の子でしたが、女の子にとって大事なお腹を蹴られたこともあります。母も姉も同じように暴力にさらされていて、ずっと耐えていました」
気に入らないことがあると機嫌が悪くなる。思っていることを相手に伝わるように表現することができない。伝わらないとイライラしてしまって相手を殴ってしまう。何が気に障って殴りかかったり物を投げつけてくるかわからない。
そんな父親だった。
子どもたちをいたわってくれた母
「父はとても尊敬できる人間ではありませんでした。自分のなかに父の血が半分流れているんだと思うだけで情けなくて」
「私は父と似ているんだと思います。人と接するのがあまり得意じゃないところは」
父と似ている・・・・・・。それだけで生きているのが嫌になったこともある。
「しかも、父は働かない人でした。私たち姉妹3人を学校に行かせてくれていたのは母です」
「父は働きに出てもすぐにトラブルを起こして帰ってくる人でした。背中に龍の刺青があって、小指がない人だったので・・・・・・」
そして、父は亡くなった。
「亡くなったときには特に何も言いませんでしたが、姉たちも私もあとからそれぞれ別の場所で異口同音に、『死んでよかった』『早く死ねって思ってた』と話していたことが最近わかりました」
みんな同じ想いだった。
「父がそんな人だったので、母が私たちを必死で育ててくれたんです」
ひとりで家族を養い、いつも父親から虐げられた子供たちをいたわってくれていた母。
その存在は、とてつもなく大きかった。
03母がいたから、いまの自分がある
同僚の赤ん坊を
肝っ玉が強くて、学はないけど弁は立つ人だった。
「あるとき、母の勤め先の若い人たちがライバル会社に引き抜かれてしまって、母が『なんてことするんだ、うちの会社の子たちを返せ』って言いに行ったそうなんです」
「そしたら、自分の会社の人を連れ戻しただけでなく、ライバル会社の人まで付いて来ちゃったっていうことがありました」
「身内のことを良く言うのは気が引けるんですが、すごいなって思いましたね(笑)」
また、同じ勤め先で働いていた女性が赤ん坊を連れて職場に来ていたのを見て、その人が働いているあいだ、自宅で赤ん坊を預かったこともあった。
しかし、あるとき、その女性が失踪してしまうという事件が起こった。
捜索願いを出すなどしてようやく発見されたが、母親であるその女性は赤ん坊を育てられるような人間ではなく、赤ん坊を渡すことはとてもできなかった。そこで、里親になると申し出たのだ。
そうして高校2年生のときに突然、戸籍上はつながりのない0歳の弟ができた。
母は、誰よりも情が深く、責任感の強い女性だった。
母が買ってくれた制服
しかし、その母が姿を消したことがあった。
父との言い合いの末、溜まりに溜まったものが爆発し、味噌汁の鍋を引っくり返して、着の身着のままで出ていってしまったのだ。
「あの母が小さな子を残して出て行ったので、よっぽどのことだったんだと思います。幸い、しばらくして発見され、父が頭を下げて一ヶ月後には帰ってきてくれました」
「その一ヶ月はバス会社の寮母として住み込みで働いていたらしいんですが、退職して家に帰るときに『おばちゃん、ありがとう』って花束をもらってました」
「たった一ヶ月しかいなかったのに、あんたどれだけのことしたのっていう(笑)」
そして、母が姿を消したタイミングで、子どもの面倒や家事をするために大学を辞め、働くことを決心した。
しかし、そのことは少しも後悔していない。
「家のことをする人がほかにいなかったし、お金が必要だったので仕方がありません。いいんです、大学生気分もちょっとは味わえたし(笑)」
「中学校の制服も、スカートをはくのは嫌だったけど、母が昼も夜も働いて、やっと買ってくれた制服だったから着ました。着たくないなんて、とてもじゃないけど言えません」
「小学生のときは一度もスカートなんてはいたことなかったので、周りから『ほんとにはくの?』って訊かれたし、入学式では指をさされましたけど(笑)」
「周りも自分も、そのうち慣れますしね。いまは、セーラー服を着ておいてよかったなって思っています」
母がいなければ生きていなかったかもしれない。
母には感謝しかない。
04話す代わりに書いて伝える
二次元オタク
「人と接するのはあまり得意じゃない」
実は、二十歳になるまでファーストフード店で注文することさえできなかった。
探している本があっても書店で取り扱いがあるかどうかを店員に訊くこともできなかった。人と話すのが極端に苦手だったのだ。
しかし、文章を書くのはずっと好きだった。
10歳の頃から小説を書くことを志して、表現の練習のためにとにかくさまざまなものを文章に書き起こしていった。
例えばドラマを観ながらそれを文章化し、しばらくしてから録画したものを観直して、自分が書いた表現が適切かどうかをチェックするといったような、訓練めいたことを行っていた。
「話すのが苦手なぶん、書くほうに進んでいったんだと思います。子どもの頃は物語をつくるということができなくて“とにかく書く”ことを続けていて、高校生になってようやく物語をつくるようになりました」
「あの頃から私はすでにオタクでしたね」
「漫画もアニメもアイドルも、二次元系はだいたい好きでした。私にとってはアイドルも二次元です(笑)」
小説を書き始める
アイドルでは、学生の頃に一世を風靡していた「たのきんトリオ」が好きだった。
双子の姉の片方はハードロック、もう片方は演歌が好きだった。どちらの影響も受けつつも、我が道を進んでアイドル好きとなった。
「たのきんトリオ」ではマッチ(近藤真彦)さんのファン。ちょっと不良っぽい雰囲気が女性だけでなく男性にも人気があったという、マッチさんに憧れていた。
「学生時代に仲のよかったグループでは、恋バナなんてすることはなかったですね。いつも漫画かアニメの話ばかりで。私もオタクだったし、友人たちもオタクだったし」
「物語が好きだったんです。絵本であろうと、漫画であろうと。映画も小説も舞台劇も全部好きでした」
そして、18歳で本格的に小説を書き始める。
33歳のときに三条裕名義で「Badi小説大賞特別賞」を受賞、翌年には衛澤創名義で商業誌での連載を手がけるようになり、個人作品集を発売した。
「書いているときは、書くことに没頭しています。書くことが楽しいと思えるようになったのは、連載がスタートしたくらいから」
以前は書くことに必死で、楽しいかどうかなんて考える余裕はなかった。
いまは、書くことがとにかく楽しい。
05うつ病と上手く付き合いながら
体を起こすことができない
現在、仕事として小説などを書きながら、性的マイノリティに関する講演をしながら、実は、長い間抱えている病がある。
「もう、いつからかはわかりません。思えば小学生のときからずっとだったように思います」
「正式に『うつ病』だと診断されたのは1995年の1月。忘れもしない阪神大震災のその日でした」
生活費を稼ぐために大学を退学したあと、工場の組立工や海上自衛官、テーマパークのスイーパーなど、いくつかの仕事を務めた。
しかしある日の朝、突然起き上がれなくなってしまったのだ。
体がひどく重くて起こすことができない。
働くどころか自宅を出ることすらできない状態だから、電話のある場所まで必死で這って行って会社に電話をかけ、「休みます」と伝える。
これが何日も続いた。
動けないため仕事にも病院にも行けず、このままでは生命が危ないと思って “いのちの電話” に連絡するも「病院に行ってください」と言われるだけだった。
そんな風に倒れて間もなく、半年間入院することになる。
それでも症状は良くならず、一度退院した半年後に再入院することになり、さらに半年間、病院で過ごした。
調子が悪くて当たり前
「うつで倒れて、つごう一年間入院したことをもって、自分は一回死んだんだと思っています」
「倒れる以前の自分といまの私はものごとの捉え方や考え方が、まったく違います。それこそ別人のように」
「以前の私は、○○しなくちゃいけない、って自分を縛り付けるような考え方をしていました。そのせいで、しんどくなってしまって、最終的に倒れてしまったんだと」
患ったばかりのときは、しんどかった。
なぜ自分がこんな状態になるのかがわからなかったし、いつまたそうなるかもわからなかったから。
「いまは、木の芽時とか秋口とか、季節の変わり目には調子が悪くなるものだとわかっていて、その時期には予定を入れないようにするなど自分で調整しているので、そこまでしんどくはありません」
「いつ悪くなるのか、どうして悪くなるのかではなくて、調子が悪いのが当たり前なんだ、と思っておいたほうがラクなんです」
「私のうつ病は慢性化してしまっていますので、治そうとするより上手にお付き合いしていく方法を考える方がずっと建設的です」
現在はうつ病と上手く付き合いながら執筆や講演を主な仕事としているが、かつての仕事で「辞めなきゃよかった」と特に後悔しているものがある。
それは海上自衛官。
給料はとてもよかったし、福利厚生も整っていたし、気持ちを分かち合える同期にも恵まれていた。
それに、漫画『沈黙の艦隊』の影響から海上自衛隊への憧れもあった。
それでも自衛官を辞めた理由のひとつが制服だった。女性自衛官としてタイトスカートの制服を着るのが苦痛だったのだ。
もう、女性の体では生きられない。
28歳のとき、ホルモン治療を開始した。
<<<後編 2017/04/30/Sun>>>
INDEX
06 性同一性障害は体の障害
07 欠けた部分を取り戻す
08 運命の人には一生会わない
09 地元の性的マイノリティのために
10 困ったら、食べて寝ること

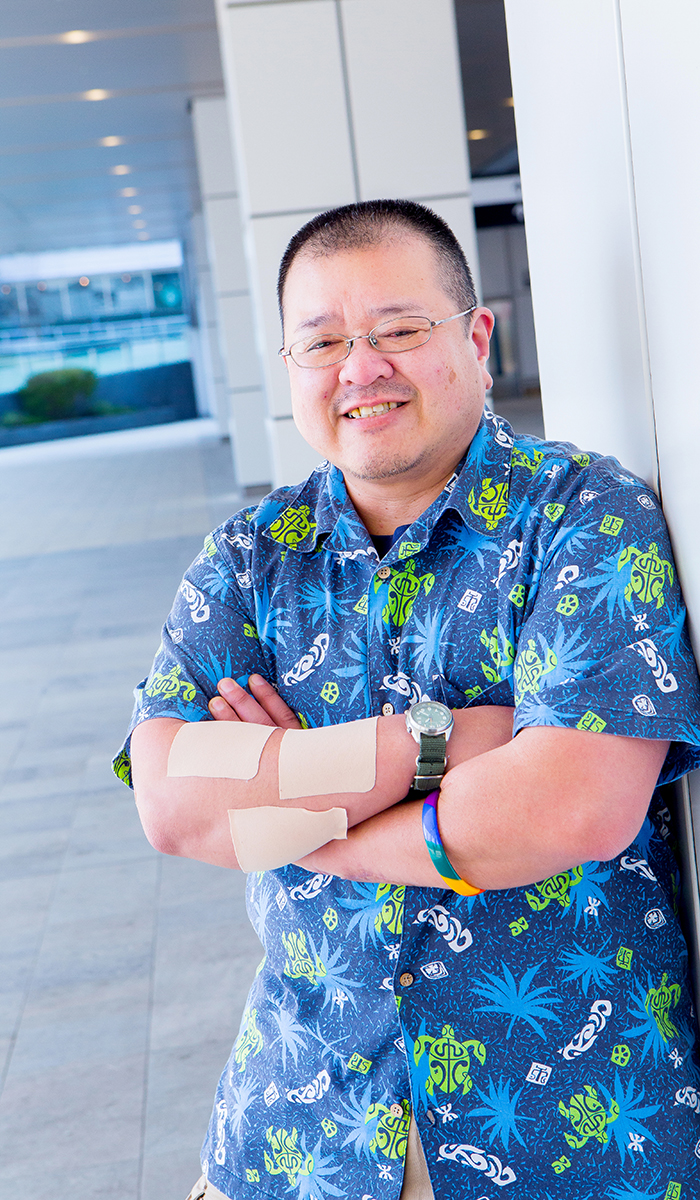





.jpg)
