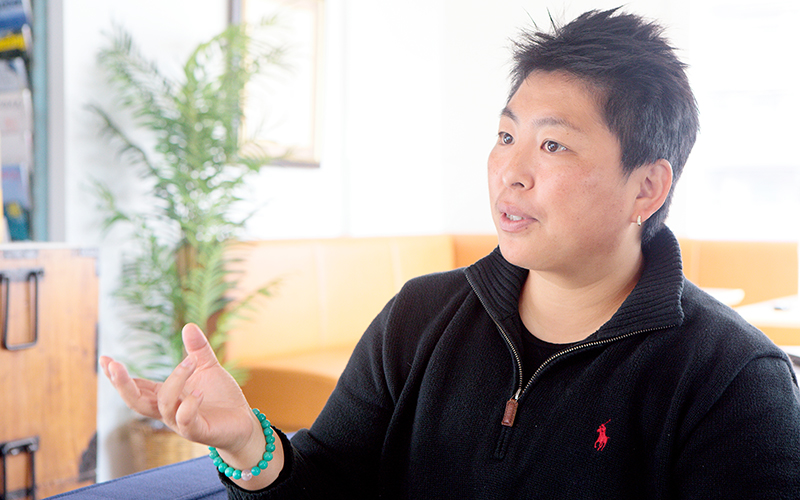02 共学だけど女子生徒しかいない
03 訪れた第一のモテキ
04 かけがえのない男性との出会い
05 大人になんかなりたくない
==================(後編)========================
06 学び舎を出て、新たな世界に
07 自分らしく、社会人としての第一歩
08 疑心暗鬼の日々のなかで
09 母へのカミングアウト
10 曖昧な自分も受け入れていこう
01親の顔色を伺って過ごした幼少期
厳格な父
長女として生を受けた。一人っ子として育つ。
父親は大手ゼネコン勤務、母親も働きに出ていたから、お金に困った記憶はない。家族のために熱心に働く父親の姿は、幼い頃から自分の憧れでもあった。
「とにかく外では、感じのいい人でした。会社でも、部下に慕われていたようです」
「ただ娘に対しては “The オヤジ” って感じでした。聞き分けが悪いと平気で手が飛んできました」
「家の中では男尊女卑的な思考をぷんぷん撒き散らす人で、母に対しても厳しかったです」
それでもどこか、どっしりと構え、悠々としている。家の中での行動は荒いけど、しっかりと家庭を守り、頼り甲斐もある。
少々考えに偏りがあるかもしれないが、その気骨ある佇まいこそ、男の生き方なのかもしれない。幼いながらにそう感じていた。
「小さいときは怖いだけの存在だったけど、大人になった今では、意外と面倒見がよくて、会社でも兄貴肌だったのかも、と思います」
「最近、自分が性同一性障害だとカミングアウトしたときの反応を鑑みても、情の深い人だと思うんです」
「女の子だからのんびり学ばせたい」と、父は娘を私立の幼稚舎に入れた。
中学からは女子校となる学校だが、小学校までは共学だった。
けれどたまたま、同学年に男子はいなかった。
そんなこともあって、身近にいる男性といえば父親だけ。いつしか自分の理想の男性像は父親になっていた。
このことが後々、自分に深い苦しみをもたらすことになる。
憤る母
物心ついた時から、自分のセクシュアリティに疑問を抱いていた。
「女として生まれたけど、きっと違うんだろうな」。
当時、そう言葉にできたかはわからないが、自分が女であることに居心地の悪さを感じてはいた。
「あれは4歳くらいの時だったかな。母とスーパーマーケットに出かけたら、試食販売のおばちゃんに『僕、どうぞ』ってウィンナーを渡されたんです」
きっとおばさんは、髪の短い自分を男の子と信じて疑わなかったのだろう。
その瞬間、とても嬉しかったことは覚えている。
加えて「やっぱり自分は女の子じゃなく、男の子なんだ」とも。
「どうして自分にはちんちんが生えてこないんだろうとか、そういう違和感を抱いたことはなかったけど、自分は男なんだと生まれながらに思い込んでいました」
「『僕』って呼ばれたことも、嬉しかったんです」
しかし母は自分とは違う反応だった。
「『うちの子は女の子です!』と全力で否定していました」
「それを見て、女の子である自分が男の子に見られるのは良くないことなんだ、と初めて思いました。間違われて嬉しいって、思っちゃいけないんだって」
何よりも母親の憤った表情が怖かった。
もうあんな顔は見たくなかった。
「だから自分の方が間違ってるんだ、って言い聞かせることにしました。母に悲しい思いをさせちゃいけないとも思ったから」
「それに親に嫌われるようなことは、やっぱり考えちゃいけないとも感じました」
02共学だけど女子生徒しかいない
男子がいない
系列の幼稚園から小学校に上がった。
共学なのに男子生徒がひとりも入ってこなかった。
30人のクラスが3学級。90人全てが女の子だ。
中等・高等部は、県内でお嬢様校と名の知れた私立。当然小学校にも清楚なデザインの制服があった。
「制服のスカートを履くのは、不思議と抵抗感がなかったんです。高学年になると、逆にスケバンに憧れて、嬉々として身につけていた気がします」
学校だけではない。家庭や地元でも男性の影が薄かった。
両親共働きなので、学校が終わったら地元の友達と外遊びしたかったが、公立に通っていないため、つるんでくれる人が近くにはいなかった。
だから家でひとり絵を描いた。工作もして過ごした。
結果として、学校でも家でも、父親以外の男性と接することがなかった。
男の子がズボンを履いて生き生きと遊んでいるのを直視せずに済んだ分、制服のスカートを履いている自分に違和感を持たずに過ごせたのかもしれない。
ただ私服のスカートには違和感があった。
でも母親が買ってきてくれるから、我慢して履いていた。
「自分がプライベートでスカートを履いているときの写真は、どれも表情がブスっとしているんですよね(笑)」
「写真屋さんから現像が上がってくるたびに、母は『何でこんなに嫌そうな顔をして写ってるの?』って言っていましたね」
女子が好きは普通
小学校ではサッカークラブに入っていた。
女子ばかりの集団の中でも目立つ方で、男っぽい、かっこいいキャラだった。
「普通に女の子を好きになっていました。とくに隠すことなく、○○ちゃんが好きだ、と言っていましたね」
「周りの同級生も、自分がどの子を好きか知っていたし、そのことが特に変なだとも思っていませんでした」
極めて男の子と接触する機会の少ない環境だった。
人間関係の全てが女子だけで完結していた。
03訪れた第一のモテキ
外部の目
中学校に上がると、他の小学校から新入生が加わり、50人×4クラスになった。
「外部から入ってきた子たちは、どこかしら『女ばっかで気持ち悪い』という冷めた目でした。女の子だけでイチャイチャしている雰囲気が奇妙に見えたみたいで」
外部生は、自分を取り巻く環境をも変え始めた。
「思春期に差し掛かったこと、外部から別の世界を知った女子が入ってきたこともあって、同級生もだんだん色気付いてきましたね。他校の男子との恋バナなんかも耳に入ってきて」
とくに興味はなかったけれど、話を合わせないと周りに違和感を与えてしまう。
自分が女性らしくないと思われ、変な人だと感じられることは、どうしても避けたかった。
幼い頃、母が男と間違われた自分に憤ったように、同級生もまた、自分に好奇の目を向け始めるかもしれない、と察したからだ。
「『良佳はバレンタインデー、誰にチョコをあげるの?』と聞かれて『そんなの知らねーよ!!』って言いたかったんですが。『いつもバス停にいる、あのかっこいい男子にあげようかな?』って答えていました」
「バレンタインデー当日、一応チョコをカバンに入れて、友達と一緒にバス停に向かったら、たまたまその日は彼がいなかった。あーよかった、ってホッとしましたよ(笑)」
男になんか興味ない、嫌々ながらも恋する乙女たちとつるむのには理由があった。
そうやって女の子と混じることで安心も得られたからだ。
「もしこのまま、同級生のように普通の女性になれたら、幸せになれるのかもと感じていました」
裏を返せば、今のままでは真っ当に生きられないと思っていた。
当時はまだ性同一性障害という言葉すら知らなかった。
付き合ってやるよ!
女性への振り戻しを感じながらも、やはり心は男だった。
小学生の頃は「好きだ」と口にしていただけだったが、中学生になると、いよいよ女子と交際し始めた。
「相手はストレートの子ばかりでした。だいたいは自分から『好きなんだけど』と告白していました」
「その時代はすでにバスケットに打ち込んでいるボーイッシュな女子だったからか、付き合うと、相手の子は自分のことを彼氏のように慕ってくれました」
ときには彼女がいるのに、別の女子からも言い寄られることがあった。
「『他に相手がいてもいいなら、付き合ってやるよ』と豪語して、受け入れたこともあります。あの頃は廊下を通るだけで、同級生にキャーキャー言われるから、楽しかったですね」
「この世の春です(笑)」
男子との接点が少ない、女子校独特のノリもあったのだろうか。
男子のような女子ということで、とにかくモテた。
「どんな子と付き合っても、彼女からは男性であることを常に求められました。だから一緒に出かける時も、周囲から自分は女だって絶対に思われたくなかったです」
「成長期で胸が大きくなるのが悩みの種だったけど、タンクトップを着込んで、必死になって隠していました」
04かけがえのない男性との出会い
自分と同じかも
実は小学生の頃から、自分と同じセクシュアリティかもしれない、という人物が存在した。
「同じ学年にFTMっぽい子がいて。そのうちなんとなく、友達になりました。けれど互いに互いがそうだと分かっていても、それを口にして共有することはなかったんです」
胸の内を告白しなかった理由は、未だに分からない。それでも以心伝心、互いに状況を察することはできた。
中学を卒業して、そのまま高等部に上がった。
引き続き、同級生からモテる日々だったが、ある男性が目の前に現れた。
「そのFTMっぽい同級生の幼馴染みで2、3歳上の男の人です。なんとなく流れで、彼と付き合うことになったんです。
初めての彼氏
「彼は、彼氏というより、頼りがいのある兄のような存在でした」
「男性といえば父しか知らなかったので、不安がなかったわけではないけれど、自分を繕わなくてもいい、素のまま一緒にいられる相手でした」
心から好きで付き合ったわけではない。
自分も思春期で自我が芽生えはじめ、女子が女子と付き合うなんておかしいんじゃないか、周りに変な目で見られるのではないか、と恐れ始めていた頃だった。ちょうどカモフラージュに良かったのだ。
「もし『お前、レズ?』って思われても、『彼氏がいるから違うよ』と言えばいいわけですから」
幸い、彼は3ヶ月に1回デートすれば文句は言わなかった。
「毎回、帰り際にキスされて、イヤだなとは思っていました」
「たまにしか会えなくても『友達を大切にするお前がいい』って言ってくれるから、本当に優しい人、意地悪な言い方をすれば、とても都合のいい人だったんですよね」
女子校では人気モノだけど、男の子から見たら、オトコオンナで気持ち悪いって思われるんじゃないかという恐怖感も抱いていた。
そんな中、彼が普通に接してくれたことは、自信にも繋がった。
「彼の前でだけ、完全に素直な自分でいられたんだと、今では思います。同級生の女子に対して自分がしていたように、好かれようと頑張る必要もなかったし」
「女らしいも男らしいもない、だたの『白井良佳』でいられたんです」
彼は、自然に寄り添ってくれる存在だった。
「嫌いじゃないし、彼と付き合っていれば親も安心するだろうと感じました。この人となら、自分を圧し殺しても付き合えるって思ったんですよね」
でもやはり異性としては好きになれなかった。
大学に進学する頃には互いが多忙になり、すれ違いから別れることになる。
「再会できるなら、自分のセクシュアリティも含めて全てを打ち明け、謝りたい」
「人生のある時期、自分にとってかけがえのない存在でした」
05大人になんかなりたくない
漠然とした不安
女子校の中で同性と付き合ううちに、自分は男なんだという気持ちがますます強くなった。
一方で、これは錯覚なんだという思いも抱き始める。
「自分は男だと思い込んでいるけど、男になれるわけがないんだから、と考えていました。今の自分は間違っているんだとも思っていました」
「今は女子校だからいいけど、大人になったら、そんな訳にはいかない。OLになれないなら、オナベとして二丁目で働くか、トラック運転手になるしかない、と将来を悲観していました」
そんなとき目にしたのが、埼玉医科大学で日本初の性別適合手術(SRS)が行われたというニュースだ。
「性同一性障害という言葉を初めて知りました。でも『手術』という言葉に怖くなって、手術なんてできないと思いました」
「同級生の女子の前で強がっていても、基本、小心者なんです」
「でも女であり続けるのは嫌でした。かといって中性だと名乗るのも嫌だし。自分の性が定まらず、胸が塞がるような思いになりました」
また性別適合手術という可能性を知って、逆に煮え切らない自分に苦しむ羽目にもなった。
「埼玉医大のSRSのニュースは、家で両親とテレビを観ている時に知ったんです。一方的に気まずさを感じて、ドキドキしました」
「そんな時、母が『よっちゃんテレビに出ている人と同じような服を着てるけど、アレじゃないよね?』って聞いてきたんです」
違うよ、と完全否定した。
自分がGIDだなんて、親には言えない。絶対に言えないと再び確信した瞬間だった。
迫る旅立ちの日
慣れ親しんだ、この女子校を巣立つのも億劫だった。
「ある時、保健室の先生に『大人になったらGパンの下に靴下じゃなくて、ストッキング履かないといけないんでしょ』って、話したこともありました(笑)」
「自分の勘違いに先生はクスクス笑ってたけど、ああこの穏やかな日々もあと少しで終了、と思うと切なくて」
卒業を前に、進路も決めなければならなかった。
進学か就職か。
決断の時は迫っていた。
<<<後編 2017/02/06/Mon>>>
INDEX
06 学び舎を出て、新たな世界に
07 自分らしく、社会人としての第一歩
08 疑心暗鬼の日々のなかで
09 母へのカミングアウト
10 曖昧な自分も受け入れていこう