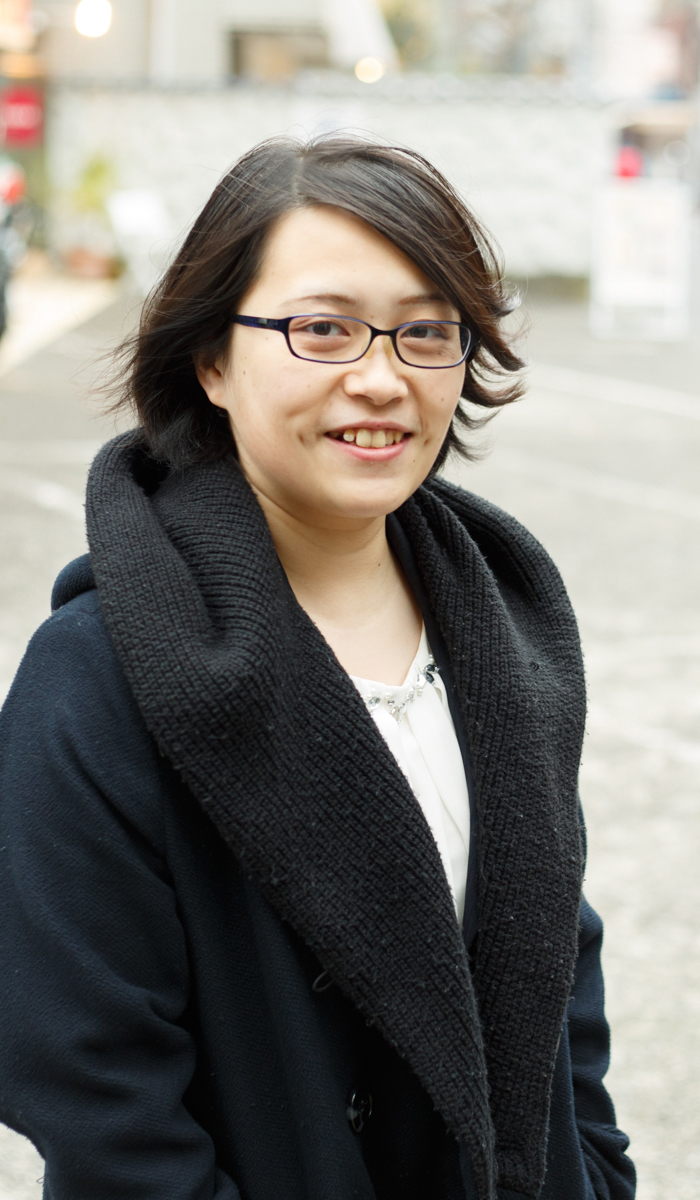02 卓球人生のはじまり
03 人間は、なんて嫌な生き物なのか
04 初めての親友、初めての恋人
05 自分はいったい何者なのだろう
==================(後編)========================
06 ”居場所” が自分のキーワードに
07 卓球を卒業、新たな世界へ
08 今しかできないことだから、全力で
09 LGBT就活の実態
10 いよいよ次なるステージへ
01誰にも本音が言えない

口をきかない子
小さい頃から無口だった。
ひとりっ子だから、家の中に話し相手がいなかった、ということもある。
「父親や母親はいましたけど、自分が思っていることを言えるような関係ではなかったんです」
とくに母親との間には、会話というものがなかった。
「母親に何を言われても『うん』『そうだね』と、ただ相づちを打つだけ。逆らって口ごたえすることもありませんでした」
「とにかく、母親の機嫌を損ねるのが嫌だった。というか、怖かったんです」
しつけは厳しかったように思う。
「なかでも時間に厳しくて、宿題は◯時までにやりなさい、◯時までに絶対に帰ってきなさいと、こと細かに言われていました」
夕方5時半になると、街にチャイムが響いた。
「普通、チャイムが鳴ったら『さあ、帰ろう』ですよね。でも母は、チャイムが鳴った時には家にいるようにしなさい、という人だったんです」
「思春期が近づいてくると、そんな母親に対してイライラすることもありましたけど、不満を口にしたり手が出たりということはなかったですね」
言わないほうが正しい
言いたいことを言えない、ということについても、つらいと思ったことはなかった。
「自分の本音を言わないほうが正しい、と思っていたんです」
母親はすごくお酒が好きで、かなり量を飲んだ。
当然酔っ払い、感情の起伏が激しくなる。
「喜ぶにせよ怒るにせよ、一度感情が高ぶると自分でもコントロールできなくなってしまって」
「そんな母親の姿を見るのが、すごく嫌でした」
子どもながらに、「女の人が酔っ払うのって、よくないな」「感情を表に出すのはよくないな」と思った。
だから自分も、感情を外に出さないことに。
ますます口数が減り、誰から見ても ”おとなしい子” になった。
02卓球人生のはじまり
4歳の時の ”温泉卓球” がきっかけに
4歳のある日、家族3人で旅行に出かけた。
目的地は、温泉。
その旅館には卓球台があり、みんな、浴衣姿で卓球を楽しんでいた。
自分も、親から「これでやるんだぞ」とラケットを渡され、見よう見まねでやってみた。
「なぜなのかうまく説明できないんですけど、とにかくものすごく楽しかったんです」
それまで、親に頼みごとをしたことなんて一度もないのに、「どうしても卓球がやりたい」と訴え続けた。
母親はずっと「そんなこと言ったって、どうせ三日坊主でやめるでしょ」と、しばらく相手にしてくれなかった。
粘りに粘って小学4年生の時、ついに卓球教室に通えることに。
「教室といっても、近所のおじいちゃんおばあちゃんが集まって、健康のために卓球をしている同好会のようなものでした」
「指導者がいるわけでもなく、みなさんが孫に手ほどきをするような感じで、私の世話を焼いてくれて(笑)」
そこでもほとんど口をきかない子だった。
「みなさんには『首ふり人形か』と言われて(笑)。でも、かわいがってもらえましたし、何より卓球が楽しくて通い続けていました」
大会に出れば優勝、の日々
肌に合ったのか、卓球の腕はめきめき上達。
周囲の勧めもあり、5年生から小学生対象の試合に出るようになった。
「そうしたら、出る大会すべて優勝してしまって。そんなに努力したわけではなく、ただ好きで卓球をしていただけなんですけど・・・・・・」
向かうところ敵なしの状態で、6年生の時には全国大会まで勝ち進んだ。
しかしそこで、自分が井の中の蛙だったことを知る。
「みごとにボコボコにされました(笑)」
一方、同年代でこんなに強い子がいることに感動し、彼らと一緒にプレーきたことがうれしかった。
「ただ、試合に負けたことは悔しかったので、家に帰ってめずらしく母親に『悔しかったー!』って感情を露わにしたんです」
母親は「あんたの実力はそんなもんでしょ。もう辞める?」と言ったが、負けて悔しいからこそ、もっともっと卓球がしたい。
そこで、大会で知り合った卓球友だちに「一緒に来ない?」と誘ってもらった卓球クラブに通うことに。
卓球人生がはじまった。
03人間は、なんて嫌な生きものなのか

自分には卓球があって、よかった
卓球教室は、電車に乗って1時間のところにあった。
往復2時間プラス、練習が2時間。当然、部活をする時間はないので、中学では帰宅部に。
「本格的に練習をはじめてようやく、卓球は、ただラケットを振って球を打ってるだけでは強くなれないんだ、ということを知りました」
まずは走り込んで基礎体力をつける。そして、瞬発力や持久力をつけるために筋トレを。
練習は苦しかったが確実に実力はつき、大会に出るたびに表彰台に上がった。
「卓球漬けの毎日でしたし、相変わらず感情を表に出さず人とも話さなかったので、クラスでは浮いていましたけど」
ただ、逆にそれがよかったのかもしれない。
当時、学校にはいじめの嵐が吹き荒れていて、自分のクラスでも入れ替わり立ち替わり、つねに誰かしらがいじめの対象になっていた。
「でも、私は学校が終わるとすぐにいなくなるし、卓球漬けで浮きすぎていたのか(笑)、いじめられなかったんです」
卓球という、打ち込めるものがあって本当によかった、と今でも思う。
ただひとり、仲よくなれた友だちが・・・
次は誰がいじめられるのかと戦々恐々とした雰囲気が漂うなか、1人だけ、近所に住む同級生と仲よくなれた。
それなのに。
ある日突然、彼女もいじめの標的とされ、その苦しみから彼女は自ら命を絶ってしまった。
いつ自分がいじめられるともわからない環境。
自分を守るには ”巻き込まれないこと” が精一杯。
傍観しているしかなかったが、彼女の死はこたえた。
さらに不幸が重なる。
「卓球の関東大会に出ることになって、引率として中学の先生が一緒に試合に行くことになっていたんです。そうしたら、大会の前日にその先生がマンションから飛び降りてしまって」
急遽、別の先生が引率してくれることになったが、ショックだった。
「人って人を傷つけるんだ、嫌な生きものだなと思って、ますます誰とも話さなくなりました」
中学を卒業すると、卓球の推薦枠でスポーツの盛んな高校へ進学。
ほとんどのクラブがインターハイの常連で、優勝旗を持って帰ることが多い強豪校だった。
「生徒のほとんどが、それぞれ部活に打ち込んでいたから、クラスではお互い、人にはあまり興味がないというか(笑)。おかげで、浮いた存在にはなりませんでした」
実際のところ、学校にいる間も卓球をしている時間が長かった。
だから、部活以外の人と話をする機会がなかった。
「お昼も部室で食べることがほとんどだったので、クラスで誰かと特に仲よくなる、ということもなかったんです」
「クラスの中には、友だちと親しく付き合う人はもちろんいたし、体育祭とかイベントで盛り上がってる雰囲気もありましたね」
「私はみんなと濃厚につながる感じはなくて、何か連絡があるとメールでやりとりする程度でした」
人と人が関わると傷つけあう。
だったら関わらないほうがいいと思っていたから、さびしくはなかった。
何より、自分には卓球がある。
04初めての親友、初めての恋人
人を信頼するということ
ところが高校1年生のクリスマスの日、試合中に足の骨を折ってしまった。
教室は校舎の4階にあったが、エスカレーターもエレベータもない。
階段を使うしかなかったが、松葉杖をつきながら荷物を持って階段を上がるなんて、とうてい無理なことだった。
そんな中、クラスの子が1人、心配してメールをくれた子がいた。
彼女に「これじゃあ階段上れないから、学校には行かない」とメールすると、「足以外は元気なんでしょ。じゃあ、来れば?」と答えが返ってきた。
「そして、『とりあえず明日、8時◯分に階段の下で待ってて』と」
翌日、約束の時間までに学校に行き、彼女に言われたとおり場所で待っていた。
クラスメートたちが「おはよう」と言いながら、目の前を通り過ぎて行く。
彼女は、なかなか来ない。
「やっぱり無理だったかな」
彼女はバスケットボール部に所属していて、卓球部と同様、毎日朝練があった。それを考えると、約束の時間には間に合わないかもしれない。
とその時、彼女がやって来た。
「おはよう!ごめんごめん、遅れて」
「彼女はそう言うと私の荷物を持ち、私のことをおぶって4階まで階段を上がってくれたんです」
うれしかった。
「人を信頼するってこういうことなんだと、その時に初めて知りました」
ありのままの自分でいられる心地よさ
この日を境に、学校生活がガラリと変わった。
それまで、クラスの中で話をする相手がいなかったから、お昼ごはんは部室で部活の仲間と食べていた。
「部活の練習中はもちろん部室でも私語は禁止だったので、みんな、ただ黙ってもぐもぐ食べていただけなんですけど(笑)」
次の日からは、親友になった彼女と移動教室はいつも一緒。お昼もたまに2人で楽しんだ。
「それまで、人と話せないことをつらいと思ったことはなかったんですが、親友ができてから、人と会話をすることの楽しさを知りました」
ふたりで、哲学的なことばかりしゃべっていた。
「学校ってなぜ行くんだろうね、人って何なんだろうね、どんなときに幸せを感じる? とか」
親友には自分の考えていること、感じていることを何でも話せた。
ありのままの自分でいられるのが心地いい。
彼女も、自分と同じ様子だった。
「親友は、すごく頭がよくて人当たりもいい。だからみんなに『やさしいよね』と言われていました」
「でも私は、彼女のことをよく知るまではずっと、どうしてか彼女のことを怖いと思っていたんです」
人前では明るく振る舞っているけれど、本当は何か暗い闇を抱えているのでは‥‥‥?
でも、仲よくなってわかった。
親友の中にある暗い部分は、闇ではなくて「弱さ」だった。
「弱くて傷つきやすいけど、がんばって明るくして、みんなにやさしくしている」
「だから私は、彼女に『やさしい』なんて言ったことはなくて、わざと『暗い』『怖い』と言っていたんです」
親友は「本当の私をわかってもらえて、うれしい」とよろこんだ。
ふたりの信頼関係はどんどん深まっていった。
女の子同士がつきあうのは「普通」だと思っていた
親友ができてから、人と話しをするのがおもしろいと思うようになり、部活仲間とも卓球以外の話をするように。
気づいたら、隣にいつも同じ子がいる。
ある日、彼女が言った。
「私たち、つきあってるよね?」
たしかに、自分も彼女に対しては、親友に対する気持ちとは違うものを感じていた。
「女友だちとしてではなくて、好き、一緒にいるとドキドキする。そうか、これが恋なんだ、と」
だから、彼女の言葉がうれしかった。
「違和感もありませんでした。自分としては、女の子とつきあうのは普通のことだと思っていましたし」
高校は共学だったが、男女交際禁止。
男子生徒と女子生徒が言葉を交わすことも、ほとんどなかった。
一緒に過ごす時間が長いほど、恋愛感情が湧きやすい。
だから、自分が彼女のことを、そして彼女が自分のことを好きになり、つきあうのは自然なこと。
だから、ふたりの関係を周囲に隠す、という発想がなかった。
「彼女も、最初のうちはそうだったんです。でも‥‥‥」
周りがざわつきはじめた。
「レズ、とか言われるようになったんです」
すると、彼女もだんだん気にしはじめた。
「やっぱりこういうのおかしいよ。違うと思う」「もう、嫌」と言って離れていった。
「その時は、自分たちの何が『違う』のか、よく理解できなかった。でも、嫌というのならしょうがないですよね」
初めての恋は、1年と少しでピリオドを打った。
05自分はいったい何者なのだろう

仲よくなった子が、たまたまFTXだった
高校進学の時と同様に、大学もいくつかから声をかけてもらい、その中から体育系の女子大に入学した。
「ありがたいことに、高校2年くらいから声をかけて頂いていたんです。だから、このままずっと卓球を続けるんだろうなと思っていました」
他に興味を持てることもないし、試合に出れば「もっと強くなりたい」と、上を目指す気持ちが強くなる。
「目標は、世界卓球選手権でした」
友だちに試合を観に来てもらいたいが、「◯◯体育館に来て」と呼んで、わざわざ来てもらうのは選手として2流だと考えていた。
「世界卓球まで勝ち進んで『今日、◯時からテレビで観ていて』と言いたかったんです」
しかし、残念ながら出場まであと一歩のところで敗退。
それでもこの道をずっと歩き続けるのだろうと、卓球に打ち込む毎日は変わらなかった。
一方、キャンパスでは新しい出会いがあった。
「大学1年の時、食堂でたまたま近くの席に座っていた子と話をするようになりました」
女子大なので学生は全員女性のはずだが、その子はネクタイを締めていて、洋服も靴もすべて男ものを身に着けていた。
体格もよくて、かっこいい。
「どうしてかな? と思っていると、その子が『自分はトランスジェンダーなんだ』って」
彼女、いや彼はFTXだったのだ。
「でもその時はまだ、トランスジェンダーとかFTXとか言われても何のことかわからなくて。LGBTという言葉も知らなかったんです」
自分で自分のことを決められるって、すごい!
ただ、トランスジェンダーについて、そして彼がFTXなのだと聞いても
「ふうん、そうなんだ」と思っただけ。
何の違和感もなかった。
「むしろ、彼の生き方をかっこいい、と思いました」
女子大でも、体育系の大学ということもあって「トランスジェンダーかも?」と思われる人は、彼以外にも何人かいたが、やはり少数派。
多くの学生は、彼らを遠巻きに見て「なんであんな格好しているわけ?」と陰で話していた。
自分も、同級生から「なんであんな子と一緒にいるの?」と言われたことがある。
そして彼自身、自分が「あんな子」と言われていることを承知していた。
「でも、何を言われていても聞き流して、堂々としていたんです」
男物のシャツを着るのもネクタイを締めるのも、「誰かに変に思われるんじゃないか」と気にして迷ったりせず、「着たいから着る」。
教育実習に行く際、「正装を」ということで他の学生たちはスーツ姿にパンプスを履くが、彼が履いていたのはメンズライクな革靴。
「そうやって、自分で自分のことを決められるのがすごい、と思いました」
いきなり「Bでしょ?」と言われて
彼のほかにもう1人、新しい友だちができた。
「彼女がいきなり、私に向かって『Bでしょ。見たらわかるよ』と言うんです」
調べてみると、彼女が言ったBとは「LGBT」のB=バイセクシュアルだということがわかった。
そこであらためて思い返してみると、たしかに、初めて恋をして交際した相手は女の子だ。
でも、大学生になってから、一度だけだが男性とつきあったこともある。
「その話をすると彼女が『ほら、やっぱり』、FTXの彼も『へえ、おもしろいね』って」
ただ、「女の子だから好き」「男性だから好き」という感覚も自分にはない。
「この人、素敵だな、一緒にいたいなと思うとき、相手の性別を意識することがまったくないんです」
ちなみに、性自認はどうかといえば自分が女性として見られることに違和感はない。
でも、子どもの頃を思い返すと、スカートを履くのが嫌だったり、ピンクやかわいい色が好きではなかったりと、嗜好は男の子っぽかった。
「考えれば考えるほど、自分はいったい何者なんだ!? ってわからなくなってしまって」
そんなことを高校時代の親友に話すと、彼女は「ただボーイッシュなだけじゃない?」と言った。
「今のところ、その言葉がいちばん自分にしっくりきますけど‥‥‥。やっぱり、よくわかりません」
「いくら考えても結論が出ないので、自分のセクシュアリティを決めないことに決めました」
だから、「結婚しないの? どんな男の人がタイプなの?」と聞かれても答えに困ることはないし、「どんな女性がいいの?」と聞かれたらいくらでも語ることができる。
「楽です(笑)」
<<<後編 2018/02/11/Sun>>>
INDEX
06 ”居場所” が自分のキーワードに
07 卓球を卒業、新たな世界へ
08 今しかできないことだから、全力で
09 LGBT就活の実態
10 いよいよ次なるステージへ