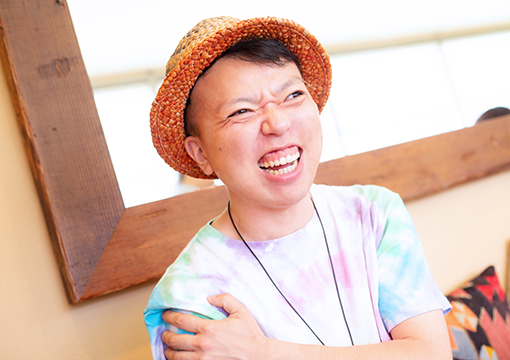02 得手・不得手
03 女子トイレへの抵抗感
04 性への違和感は「気の迷い」
05 学校に行きたくない
==================(後編)========================
06 昼の世界と夜の世界
07 自分はFTMだ
08 20歳の親孝行
09 母へのカミングアウト
10 あなたに生きていてほしい
06昼の世界と夜の世界

初めてのアルバイト
15歳の春、中学校卒業と同時に、児童精神科を退院した。
4月から定時制高校に通うことが決まっていた。
「入学前、定時制高校は卒業までたどり着けずにドロップアウトする人が多いと、周りから言われてたんです」
「卒業するためには、自分をしっかり持たなきゃいけないって」
高校を卒業すれば、専門学校や大学など、その先の道が開ける。
「だから、高校入学時の目標は『とにかく卒業すること』でした」
定時制高校は、年齢の幅が広い。みんな、昼は仕事をして、夜は学校で勉強する。
「僕も、昼間はアルバイトをしていました」
「仕事と学業の両立は大変だって言われがちですよね」
「でも、2つの世界に足を置くことで、かえってバランスが取りやすくなったんです」
アルバイト先の居酒屋には、さまざまなお客さんが来る。
中には、奇抜な服装や、目立つ髪型の人もいた。
「個性を表現して人を見ると、羨ましいなって思いました」
典型的な女の子にならなきゃいけないと思ってたけど、それが正しいわけじゃない。
「バイトを始めたことで、視野が広くなって、そういう考えが芽生えてきたんです」
ゲームへの傾倒
アルバイトは楽しかった。
接客ではなく、裏方の仕事のほうが得意だった。
「接客は、いきなりお皿が割れるとか、急に忙しくなるとか、いろいろ想定外の事態が起こるじゃないですか」
「そういうことに対応するのが難しいから、基本的には裏方」
「最初は接客で採用されても、店長が見極めて、仕込みに回してくれることが多かったですね」
3つのバイトを掛け持ちし、月7万円ほど稼ぐこともあった。
「めっちゃエンジンがかかってたと思います」
「昼間は居酒屋で仕込みをして、もう1軒仕込みの手伝いに行って・・・・・・」
「学校が終わったら1〜2時間コンビニでバイトして帰ってましたね」
「それまでずっと閉ざされた空間にいたから、自分で働いて対価を得られることが新鮮だったんだと思います」
自由に使えるお金が増えると同時に、ゲームにハマった。
「モンスターハンター」など、最新のソフトを次々購入。課金こそしなかったが、常にゲームのことばかり考えていた時期もあった。
「子どもの頃はアナログゲームしか買ってもらえなくて、テレビゲームの面白さをそのとき初めて知ったんです」
「自分で稼いだお金で、自分の好きなように使えるって最高だなって」
「のめり込んで、抜けられなくなりました(笑)」
エネルギーの枯渇
アルバイトに学校にゲーム。
中学時代を取り戻すかのように、フル稼働した。
「でも、あるときから、疲れて勉強に身が入らなくなったんです」
「あと何回休めるかなって、公欠できる日数を計算し始めました。自分でも、ちょっとマズいなと思いましたね」
たとえ学校を休んだとしても、中学までと違い「こうしなさい」「ああしなさい」と世話を焼く大人はいない。
生徒の自主性に任せるというのが、定時制高校の良いところであり、不便なところでもあった。
「僕は、ある程度レールを敷いてもらったほうが、動きやすいタイプなんです」
「『どうぞお好きに』って言われると、何をすればいいかわからなくなる」
「高校入学前に言われた『自分をしっかり持たなきゃいけない』という言葉の意味が、ようやく呑み込めました」
07自分はFTMだ
一人称の変化
小中学生のとき、自分のことを「僕」とか「俺」と呼ぶことがあった。
しかし、周りの人からは「なんか変」と言われることが多かった。
あるとき、「学校でお姉ちゃんが『俺』って言ってるよ」と、妹に家でバラされた。
「直感的に『ヤバい』と思いました」
「それからは、あまり言わないように気を付けてたんです」
高校に入学してから、また少しずつ「俺」や「僕」を使うようになる。
「無理に『私』って言うよりも、『俺』のほうがピタッとはまるなって感じたんです」
それまでは、付録目当てにティーン向けのファッション誌を買ったり、スカートを短くしたりするなど、周りの女の子と同じ行動をしようとしていた。
そうすることで、いつか自分の違和感が薄れていくのだろうと思っていた。
「でも、ムズ痒さはいつまで経っても変わりませんでした」
「自分のことを『僕』や『自分』と呼び始めて、やっと立ち位置が明確になった気がしたんです」
一人称が変わったことで、周りの女の子と同じことをしなきゃいけない、という意識が薄れていった。
自分の考え方や行動は、女性より男性に近いのではないかと、少しずつ感じ始めていた。
FTMだと確信したとき
「高校の同級生の女の子は、彼氏とのデートやファーストキスについて、すごくうれしそうに話すんです」
「周りの女の子たちも、それを聞いて盛り上がってました」
「でも、その話の何が楽しいのか、僕にはわからなかった」
「他人の恋バナを延々と聞くのは、むしろ苦痛だったんです」
その一方で、男友だちとゲームやアイドルの話をするときは、夢中になって時間を忘れるほどだった。
お金の使い途について、数人で議論になったときも、男性側の意見のほうが納得できた。
「自分はFTMだ」
友だちとたわいもない話をする中で、少しずつ確信を深めていった。
08 20歳の親孝行

家庭内一人暮らし
「とにかく高校を卒業しよう」
入学時に、確かにそう決意した。しかし、人間関係のいざこざなどが重なり、成し遂げることはできなかった。
高校を辞めたあとは気持ちがふさぎ、家族と一緒にいるのも嫌だった。1日中、一人で気ままに過ごしたいと思った。
しかしあるとき、その衝動はピタッとおさまる。
「居候みたいな感じで、自分の身の回りのことを、自分でするようになったんです」
「たとえば、『洗濯機使うよ』とお母さんに断ってから、服を洗濯して自分の部屋に干すとか」
「洗剤など日用品も、自分で買ってきたものを使ってました」
親孝行の振袖
そういった生活を始めて2年ほど経った頃、母から「一人暮らしをしてみない?」と提案された。
「発達障害が気にかかっていたんでしょうね」
「生活を回すことや、お金のやりくりに関して、経験値を早めに積んでおいたほうがいい」
「そう考えた上での提案だったんだと思います」
20歳になった年の11月から、一人暮らしをスタート。
その2ヵ月後には、成人式を迎えた。
母が忙しかったこともあり、佐々木家では、七五三などさまざまな節目で写真を撮り損ねていた。
せめて成人式という節目には、それらしい写真を残してあげたい。
「振袖を着て写真に収まることが、自分なりの親孝行じゃないかと考えました」
「本当は袴を履きたかったけど、その一言はぐっとこらえましたね」
振袖姿の写真を見て、母も祖母も「きれいだね」と喜んでくれた。
あるトランスジェンダーとの出会い
一人暮らしを始めてから、地域の老人介護施設へボランティアに行く機会が増えた。
同じように、ボランティアに来ていた人の中に、トランスジェンダーの人がいた。
その人と出会ったことが、カミングアウトのきっかけになる。
「その人は、自分のセクシュアリティをオープンにしていました」
「自分という強い芯を持っていて、自然な形で自己表現しているところに、すごく惹かれましたね」
それまで、自分のことを「俺」「僕」と呼ぶたびに、なんとなく後ろめたさを感じていた。
「でも、その人に出会って、自分のセクシュアリティを隠さなくてもいいんだなって思えたんです」
友だちなど周りの人に、正式にカミングアウトしたわけではない。
「男っぽいよね」と言われたときに、試しに「いやいや、男だし」と返してみただけだ。
「意外にも『へえ、そうなんだ』って受け入れてくれる人が多くいました」
自分が男であろうが女であろうが、変わらず接してくれる人はたくさんいる。
「いつまでも怖がって蓋をしていたら、それを知ることはできませんでした」
09母へのカミングアウト
この日のために髪をばっさり切った
母にカミングアウトしようと決めたのは、将来を見据えてのことだ。
「ホルモン治療や性別適合手術をしようと思っても、すぐに同意してもらえるとは限りませんよね」
「改名も考えていたので、カミングアウトして、どんな反応をされるか見たいと思ったんです」
琴乃という名前は、父親が付けたと母に聞いたことがある。由来は特にないらしい。
だから、改名するときは、母に名付け親になってもらいたいと思っていた。
カミングアウトの舞台は、発達障害のカウンセリングでお世話になっている病院。
主治医に協力してもらい、母との面談の最中に、手紙を渡してもらった。
「当時の僕は、髪の毛の長さが腰まであったんです。それをばっさり短髪に切りそろえました」
「さらしを巻いて、メンズの甚平を着て、自分の理想の姿をつくり上げたんです」
母が手紙を読み終えたところで、主治医に自分を呼んでもらった。
そして、母の真正面に立ち、「男として生きていきたい」と伝えた。
母からの言葉
まさかそんな話をされると思っていなかった母は、目が点の状態。
「そうなんだ」とつぶやいたあと、動揺しながらも、こう話してくれた。
「私も子どもを一人で育ててきて、仕事もバリバリやってきて」
「そういうところは男っぽいし、私にもそういう面があるかな」
セクシュアリティの問題とは、論点がズレている。
でも否定せずに、一生懸命近づこうとしてくれる。
そんな母の気持ちが、ありがたかった。
「僕のセクシュアリティについて、お母さんがどの程度理解しているかはわかりません」
「女の子らしい扱いや、女の子らしい服を着せていれば、そのうち戻ってくれるだろう、って考えているのかもしれないのは、何となく感じますね」
「改名についても話しましたが、今のところ、あまりいい返事はもらえていません」
自分自身のセクシュアリティを受け入れるのでさえ、10年以上かかった。
だから、急に理解してもらおうとは思わない。
否定されなければ、それで十分だ。
10あなたに生きていてほしい

リスクはゼロじゃない
「自分はFTMだ」と確信してから、肉体的に男性になりたいと、ずっと思い続けていた。
「銭湯や、スポーツジムの更衣室などに行くと、女性が目の前で裸になることもありますよね」
「目の前で脱がれたら、『どうしよう』ってあたふたしてしまうんです」
「見たらダメだよなって、申し訳ない思いでいっぱいになります」
ホルモン治療や性別適合手術についても調べ、いつどのようなタイミングで始めるべきか、悩んできた。
しかし、大事な人にその悩みを打ち明けたところ、返ってきたのは「どんな手術でも、リスクはゼロじゃない」という言葉だった。
「琴乃は琴乃のままでしょ」
「自分に対してありのままでいてくれるなら、リスクを負ってまで肉体を変えなくていい」
そう言われたとき、ハッとした。
「自分が、いかに両極端な考え方をしていたか気づきました」
「FTMなら肉体も男にならなきゃいけないって、心のどこかで思ってたのかもしれません」
「白と黒の中間色があってもいいということを、その人が教えてくれたんです」
肯定されることの安心感
小学5年生で学校に行けなくなってから、自分を肯定できないまま生きてきた。
自信を持てない自分に対して「そのままでいい」と声を掛けてくれる人は、何人もいた。
「でも、あなたに生きていてほしいという意味で、その言葉をかけてもらったことはなかったんです」
手術や治療を否定はしない。
なりたい姿に近づくことで、自分の性により自信が持てるようになるのかもしれない。
しかし、少なくとも自分にとっては、いますぐに解決すべき課題ではなくなった。
自分の存在を肯定されるだけで、大きな安心感を得られる。
そう気づかせてくれる人に出会えた自分は、幸せだと思う。
次の勇気へバトンをつなぐ
LGBTに限らず、マイノリティが理解を得ることは難しい。
マジョリティに合わせて、アイデンティティに蓋をしてしまった人は、たくさんいるだろう。
「いままで、地元でLGBTの当事者と出会うことは、ほぼありませんでした」
「けれども、当事者が存在しないわけではないと思うんです」
「LGBT当事者であることを否定されない環境が整えば、きっと出会う機会も増えるんじゃないかな」
どんな趣味や価値観の中にも、必ずマイノリティとマジョリティが存在する。
マジョリティだから正しく、マイノリティだから間違っているというわけでもない。
誰もがマイノリティになる可能性があり、それが、人を輝かせる個性につながることもある。
「僕は、聴覚障害と発達障害、そしてFTMという複合マイノリティです」
「自分のことを稀少な存在だと思っていたけれど、同じ障害を抱えたFTMの人と知り合うことも、案外多いんですよね」
セクシュアリティに悩む人は、勇気を出して声を上げることで、近くにいる仲間と必ず知り合うことができる。
もしも、声を上げられなくても、仲間は必ずいると知っていてほしい。
「この記事は、LGBT当事者である僕から誰かへのバトン」
「次の勇気につながったらうれしいなと思います」